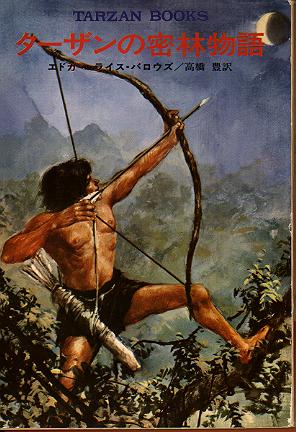 『ターザンの密林物語』は、1916年から1917年にかけてブルー・ブック誌に連載され、1919年に単行本として刊行されました。ターザン・シリーズの6番目の作品で、それぞれ主題の違った短篇物語がある流れを追って連なった、いわゆるオムニバス型式をとっています。
『ターザンの密林物語』は、1916年から1917年にかけてブルー・ブック誌に連載され、1919年に単行本として刊行されました。ターザン・シリーズの6番目の作品で、それぞれ主題の違った短篇物語がある流れを追って連なった、いわゆるオムニバス型式をとっています。この型式の小説は、基本的には短篇小説の作法によって創作しなければなりませんから、それまで長篇小説ばかり書いてきたバロウズにとって、これはまったく新しい試みでした。それだけにかなり苦心の跡が見られますが、その試練をへることによって、バロウズは作家として、少なくとも小説技法において、新境地をひらくことができたようで、これ以後の作品は、往々にして冗漫に流れることの多かった文体がひきしまり、苦渋しがちだった筆致が軽妙なタッチになり、小説の幅が広まるなど、顕著な変化が見られます。SF味の濃くなるようになったのも、このころからでした。この『ターザンの密林物語』は、そうした意味からも劃期的な作品であるばかりでなく、かれ独特の《秘境もの》の粋がここに集められていて、シリーズ中の出色の作といえると思います。
ターザン物語の特色の一つは、《大自然》の強烈な印象があることでしょう。しかし、それはかならずしも、小説の舞台がアフリカのジャングルであるためではないような気がします。バロウズの描くアフリカのジャングルは、すべて空想の所産であって、現実のものではないからです。かれは一度もアフリカの地を踏んだことがありませんし、当時のアフリカはまさに暗黒の大陸で、調べる資料も極端に乏しく、アフリカのジャングルを描写する素材を集めることさえ難しかったという事情もあったわけですが、とにかく生物学的あるいは地理学的見地からすると、ターザンの活躍するジャングルは、ときとしてアメリカ南部の森林ではないかと思われることさえあります。
ところが、わたしたちはそのような奇異なジャングルの中で展開されるターザン物語から《大自然》を感じ、《大自然》への郷愁をそそられます。これはいったいなぜなのでしょう? ターザンがアメリカのみならず世界中で圧倒的な人気を博した秘密が、おそらくその謎の中にひそんでいるにちがいありませんが、その謎を解く手がかりとして、まずターザンの系譜をたどってみることにしましょう。
バロウズは、イギリスの文豪キプリングの『ジャングル・ブック』――ご存じかもしれませんが、インドのジャングルで狼の母親の乳を吸って育った少年モウグリを主人公とした冒険小説で――そこからヒントを得てターザン物語を書きはじめたといわれます。(この問題については『ターザンと黄金の獅子』および『ターザンと蟻人間』の解説で森優氏が書いているので参照してください。)バロウズ自身もそれを認めています。そしてキプリングはバロウズを「天才的な模倣者」と批評していますが、しかしターザンの系譜は、キプリングが独断したような、単純なものではなかったのです。
ヒントを得たという点から見れば、バロウズが下敷にした古今東西の小説や伝説はほかにもさまざまあったようです。たとえば、この物語に登場するライ病やみのまじない師が二匹のハイエナといっしょに住んでいる洞穴や、伝説の国オパルなどは、イギリスの古典的な冒険小説作家サー・ライダー・ハガードの『ソロモン王の洞窟』や『洞窟の女王』が、濃い影を映しています。しかし、ハガードは青年時代にアフリカに渡って、植民事業にたずさわっていましたから、アフリカ南部の荒涼たる砂漠や原始の密林や現地人の集落などを、かなり刻明に写実的に描写しているのですが、バロウズはまるでそんな必要はないといわんばかりに、そのような描写をほとんど採りいれていません。
バロウズは舞台の背景の書割に、あらっぽいタッチで、類型的で装飾的な《大自然》の風景を書きなぐっているだけです。それは徹底したマンネリズムで、通俗的で、ときとしてはきわめて幼稚な絵です。ところが、それにもかかわらず、ターザン物語は独特な《大自然》の息吹きを、強い体臭を感じさせます。
また、ハガードの二つの作品の主人公アラン・クオーターメンは、ビクトリア王朝時代のイギリスの大衆の夢を託するにふさわしい行動人でした。ターザンも同じようにイギリスの名門貴族の子として設定されていますが、しかしターザンはイギリス人的な特徴がまったくないばかりか、いかにもアメリカ人くさい。この物語の《ジャングルのユーモア》にしても、それは洗練されたイギリス流のユーモアではなく、強いていえば、マーク・トーウェインの描いた粗野な西部男のドタバタ・ユーモアに近いものです。
いちいちそのような例証をあげるまでもなく、ターザンは実質的にはアメリカ人だといってさしつかえないでしょう。力と正義、レディ・ファースト、フェア・プレイなどを信条とする、もっともアメリカ的なスーパーマンです。つまり、バロウスはターザンにアメリカ大衆の夢を託していたわけです。
しかし、その夢はすでにアメリカでは失われていました。ターザンはその夢のためにアメリカを脱出して、原始のアフリカで生きなければならなかったのです。ターザン・シリーズの第一作では、ターザンはアフリカのジャングルを出てアメリカヘ渡りますが、《文明》によって荒廃したアメリカに失望してふたたびアフリカのジャングルヘ帰るようになります。その物語が次のような対話で終わっていることは、きわめて象徴的です。