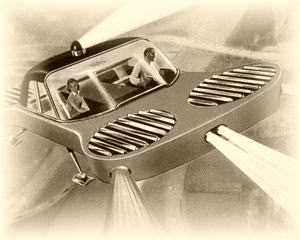
CHAPTER III
Mystery
第3章
ミステリー
e-txt:長田秀樹
訳:長田秀樹
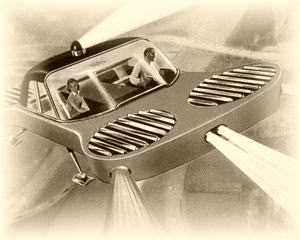
The strato police ship came, and, as Fate would have it, under the command of Lieutenant Terrance Donovan. The body of Mason Thorn was removed to the small room off the library -- a room that he had used for a study and in which was a large couch. It was laid upon the couch, near an open window. Then Terrance Donovan returned to the library. Mrs. Glassock was there, and Genevive. Percy Thorn sat on a sofa beside his aunt, who was weeping softly, trying to comfort her. Saran stood before the cold fireplace smoking a cigaret. Greeves remained beside the door to his master's study. There were three burly police officers and some of the maids and housemen also, the latter standing near the hall doorway as though momentarily expecting to be banished.
"Now," said Terrance Donovan, "I want to hear about this. Who saw the shooting,"
"No one," replied his son, "as far as I have been able to discover. The killing occurred at precisely a quarter past two," he glanced at Saran, but the latter was looking at the ceiling. Nariva was not in the room. "I was the first to reach the hall. I found Mr. Thorn lying where you found him, but on his face. It was necessary for me to turn him over to examine him for signs of life -- otherwise the body was not disturbed."
Neither Lieutenant Donovan nor Macklin had given any indication of their relationship or that they were even acquainted, owing to the fact that the latter was assuming a role necessary to the successful prosecution of his investigation and that exposure at this time would doubtless nullify all that the Department had accomplished.
"Who do you think might have had reason to wish to kill Mr. Thorn?" continued Lieutenant Donovan.
"I believe that no one could have had any reason for wishing to kill him," replied Macklin. "To my knowledge he hadn't an enemy in the world and I never heard him in altercation with anyone --" He paused. "It is my belief, sir, that the needle that killed Mr. Thorn was intended for another." As he spoke he looked directly at Saran whose eyes were now upon him, and was rewarded by a slight narrowing of the other's lids. Somehow this chance shot had gone home. Saran knew something.
"Who followed you into the hall after the needle was fired?" asked the police official.
"I did," said Saran. "Mr. Donovan was standing over the body of Mr. Thorn as I came from my room. The hall was but dimly lighted, yet sufficiently to permit me to see Mr. Donovan. He was putting something in his hip pocket as I opened the door of my room." The insinuation was obvious and that it was thoroughly understood was manifest by the sound of quick intaking of breath by several of the occupants of the library.
Macklin smiled. "You'd better have me searched, lieutenant," he said.
"I object to his being searched or questioned farther by this officer," protested Saran.
"Why?" asked Lieutenant Donovan.
"Because you are his father," replied the Assurian.
The effect of this second surprise was almost equal to that of the first. The chin of Mrs. Peabody Glassock dropped for an instant, then she smiled superciliously.
"The count must have lost his mind," she whispered to her daughter. "The very idea -- Macklin Donovan the son of a common policeman! "
Genevive turned to a police officer standing behind them. "What is the lieutenant's name?" she asked.
"Terrance Donovan, mum," replied Officer McGroarty.
Mrs. Glassock appeared slightly groggy, but she was still in the ring. "Ridiculous!" she exclaimed "He is of the Donovans of San Francisco." She looked defiantly, and crushingly at Officer McGroarty.
"Sure, mum," said he, "an' it wasn't me that was after sayin' he wasn't -- it was him over there," he nodded in the direction of Saran.
Terrance Donovan eyed the Assurian. "What makes you think this man is my son?" he demanded.
Saran hesitated. He seemed to regret that he had made the charge. He smiled deprecatingly and spread his palms before him with a shrug. "One of the servants at Three Gables told my valet. I gave the matter no thought -- scarcely believed it, in fact, until you arrived here tonight. Then I recalled."
"How does it happen that you know my name?" asked Terrance Donovan.
Saran was evidently nonplussed by the question. He realized his mistake instantly, but it was too late to remedy it. He sought to cover his confusion by a show of anger.
"It makes no difference how I know," he snapped. "I do know, and I don't purpose permitting the murderer of my friend to escape because he is the son of a police lieutenant. I demand that some other officer pursue this investigation."
Terrance Donovan nodded. "You are right," he said. "I think Captain Bushor is here now -- I just heard his ship arrive."
"He does not deny that Macklin is his son," whispered Genevive, to her mother.
"Preposterous," said Mrs. Glassock, but she said it in a small voice -- she was weakening. "I always mistrusted him," she added; "he never impressed me as one having the air of one to the manner born, as it were."
At this juncture a large man in the uniform of a captain of police entered the room. He nodded to Lieutenant Donovan and crossed to his side. The two men whispered together in low tones for a few minutes, then Captain Bushor pointed a large forefinger at John Saran.
"Do you accuse Mr. Macklin Donovan of the murder of Mason Thorn?" he asked.
"I accuse no one," replied Saran; "I merely relate what I witnessed."
"What else did you witness beside what you have told Lieutenant Donovan?"
"After the police came, and while they were carrying Mr. Thorn's body down stairs Mr. Donovan went to his room, took a piece of paper from his pocket and burned it."
Macklin Donovan looked at the speaker in surprise. Saran had spoken the truth, but how had he known?
"Perhaps," continued the Assurian, "he may have hidden his pistol at the same time -- provided of course that it was he who shot Mr. Thorn. If the pistol is not in his possession now it may be in his room. He should be searched and so should his room."
"Shure it's a dhirty frame," grumbled Officer McGroarty. "I've known Mackie Donovan since we was knee-high to nothin' at all, an' there ain't a sneaky hair in his head." He spoke in a whisper that was audible only to the Glassocks.
"Then you admit that he is the son of that person there," accused Mrs. Glassock. "I am not in the least surprised. I have said right along that he had a low face."
Genevive Glassock looked at her mother in wide-eyed astonishment. "I think he's wonderful," she said, "and I have changed my mind about marrying him." She could not resist the temptation to retaliate for the older woman's past unwelcome efforts at matchmaking.
"You will return to Philadelphia today," snapped Mrs. Glassock.
Captain Bushor was searching Macklin for a weapon -- which he did not find.
"Now we'll take a look at your room," he said. "You come along," he pointed at Saran. "The rest of you stay here. See that no one leaves the room, McGroarty."
Lieutenant Donovan glanced quickly around the library as he accompanied Bushor, Saran and Macklin toward the stairway. "Where's the butler?" he demanded suddenly.
"Why, he was here just a moment ago," replied Percy Thorn; "perhaps he's stepped into the next room," and he pointed to the study where his father's body lay. "Greeves!" he called, but there was no response.
One of the policemen stepped into the adjoining room. "There ain't no one in there," he said.
"Find him," directed the captain, as he led the way up the stairs, with Mackin Donovan at his side.
Upon the left of the landing half way up the stairs was a tall pier glass. Reflected in it, just for an instant, Macklin saw the shadowy figure of a woman dart into his room at the far end of the dimly lighted hall. He was upon the point of telling Bushor what he had seen when there flashed to his mind the realization that all the women in the house, save one, were in the library below, and that one was Nariva Saran.
An instant later they reached the head of the stairs in full view of the entire hallway. There had been no opportunity for whoever had entered his room to leave it. The hall had been lighted when last he passed through it after the officers had come, but now the lights were extinguished, the only illumination coming from the landing on the stairway. Who had extinguished them, and why? Possibly what he had just seen reflected in the mirror explained why.
The three men walked directly to Macklin's room, which, like the hall, was in darkness, although Donovan distinctly recalled that the lamp on the reading table had been lighted when he left the room. Just inside the doorway was a switch. Macklin pressed this switch and the room was flooded with light.
"I suggest that you make a very thorough search," said Saran.
"When I want any suggestions from you I'll ask you for 'em," replied Bushor, tersely. Saran subsided, scowling.
"Got a gun, Macklin?" asked the captain.
"It's in my dresser -- top drawer on the left," replied young Donovan, indicating the article of furniture with a jerk of his thumb.
Captain Bushor crossed to the dresser and opened the upper left hand drawer, in which he rummaged for a moment. "No gun here, Macklin," he said.
Macklin Donovan knitted his brows. "It was there at the instant that Mr. Thorn was killed," he said. "I had just placed it there."
The police officer continued to ransack the dresser, and then each of the other pieces of furniture in the two rooms and the closet. Nowhere could he find a pistol. Saran was quite evidently restraining a desire to speak, only with the greatest difficulty. At last he could hold his peace no longer. "Why don't you search the bed?" he demanded, eagerly.
Macklin glanced quickly toward the bed, the covers at the foot of which, he noticed for the first time, were disarranged, as though they had been pulled out from the side and hastily tucked in again. Bushor crossed to the bed and pulled the coverings aside. One by one he removed and shook them. Finally he turned the mattress completely off the springs. Saran was almost standing on tip-toe. There was no weapon there!
Young Donovan was looking at Saran, upon whom he kept his eyes as much as possible, and he saw the lock of blank surprise that crossed the Assurian's face.
All the time that the search had been going on Donovan had been awaiting the discovery of the person he had seen enter the room only a minute ahead of them. As every nook and cranny was examined without revealing any hidden presence he was reduced to a state of surprise fully equaling that which Saran had revealed when no pistol had been discovered beneath the mattress. Walking to one of the windows he looked out and examined the roof along the front of the penthouse -- there was no one there.
They returned to the library just as the officer who had been detailed to find Greeves entered the room. "I've searched the whole place, Cap'n," he said, "an he ain't here. The penthouse is being watched outside, front an' back, an' there ain't no one gone out."
Bushor nodded. "Then he must be inside," he said. He turned to the company in the room. "You'll all admit that there's something peculiar about this case. I can lock you all up on suspicion, but I don't want to do that. Right now there isn't a case against anybody, and so I'll give you your choice of remaining here under guard until morning, or goin' to the station. Under the circumstances I can't make any exceptions, and I'm stretchin' a point in lettin' you stay here. Which will it be?"
They unanimously chose to remain in the house, under guard. "Now go to your rooms and stay there." He walked from the room, beckoning Lieutenant Donovan to follow him. "I Ieft 'em here," he explained in a low voice, "because I think here is the best place to trap the murderer. He's one of 'em, but I don't know which one. Don't let any one leave the house, and say, find that damned butler. See you about eight o'clock," and he departed.空中警察の船が到着し、運命の神はテランス・ドノヴァン警部補の指揮下にそれをおいた。メイスン・ソーンの遺体は図書館から離れたところにある小さな部屋に移された――その部屋は以前から研究に使っていたところで、大きな長椅子がおいてあった。遺体は開け放たれた窓の近くにある、その長椅子の上に横たえられた。そしてテランス・ドノヴァンは図書館にとって返した。グラソック夫人はそこにいた。ジェネヴァイヴもだ。パーシィ・ソーンは声を押し殺して泣いていた叔母のそばのソファに腰掛けて、慰めようとしていた。サランは火の気のない暖炉の前でたばこをくわえて立っていた。グリーヴスは自分の主人の研究のためにドアの近くでじっとしていた。3人の頑強な警官と幾人かのメイドや下男たちもそこにいた。メイドたちは、その場からとっとと追い出されるのをいまやおそしと待ちかまえているかのように、ホールの戸口の近くに立ちつくしていた。
「さて」とテランス・ドノヴァンはいった。「この件について詳しく話してもらおうか。だれかこの銃撃を見たかね」
「誰もいやしませんよ」と警部補の息子がこたえた。「ぼくが見た限りではね。殺人は2時15分きっかりにおこなわれたんですよ」
かれはちらっとサランのほうを見たが、サランはじっと天井を見上げているだけだった。ナリヴァは部屋にはいなかった。
「ぼくが最初にホールに入ったんです。あなたも見たのとおなじ場所で、ソーンさんはうつむけになって倒れていました。生きているかどうかを確認するためにはあおむけにしなきゃならなかったんですよ――それ以外は、あの死体は何もされていません」
ドノヴァン警部補とマックリンは、まだおたがいがどういう関係なのかを明かしてはいなかったが、マックリンが判断できた限りの調査結果を報告するという重要な役割を引き受けていることと、このときに当局が成し遂げたことのすべてが間違いなく意味を失いつつあったことを暴露したという事実のせいで、すでに教えたも同然だった。
「ソーンさんに殺意を抱いていたものがいるとすれば、誰だと思うかね?」と、ドノヴァン警部補は続けた。
「殺したいと思っていた人なんていたはずがないと信じていますよ」マックリンはこたえた。「ぼくが知る限りでは、ソーンさんの敵なんてこの世の中にはいなかったし、だれかと口論していたなんてことも聞いたことがない――」
少し間をおいた。「ぼくは確信してますよ、警部補、ソーンさんの命を奪ったニードルには何か別の目的があったはずです」
いいながら、かれは自分を見つめていたサランを正面から見た。そのまぶたにかすかな軽蔑を認めたことで、かれは報われた。なんとかしてこの好機を活かさなければならない。サランは何かを知っていた。
「ニードルが撃ち込まれたあとに、きみに続いてホールに入ってきたのは誰だったかね?」と警官が訊いた。
「わたしです」とサランがいった。「わたしが自分の部屋からホールにでてきたとき、ドノヴァンくんはソーンさんの体の上に立っていました。ホールは薄暗かったけれど、それでもドノヴァンくんだということはわかりましたよ。わたしが部屋のドアを開けたとき、かれは何かをズボンのポケットに入れようとしていました」
そのほのめかしは非常にあからさまで、そのうえ完璧に理解されたことは図書館の居住者の何人かが素早く瞬間的に息をのむ音が聞こえたことからも明白だった。
マックリンは笑った。「あなたはぼくのことを逮捕して調べたほうがよさそうですよ、警部補」と、かれはいった。
「わたしはこの警察のかたがかれを調べてさらに尋問することには反対する」と、サランは抗議した。
「どういうことかね?」と、ドノヴァン警部補は訊きかえした。
「だって、あなたはかれの父親でしょう」と、そのアシュリア人はこたえた。
この2番目の驚きの効果は最初のものとほとんど等しかった。ピーボディ・グラソック夫人のあごは一瞬落ちて、それから高慢な笑いを見せた。
「計算が間違っているのに違いないわ」夫人は娘に小声で話しかけた。「すごい思いつきだこと――マックリン・ドノヴァンが公共警察官の息子だなんて!」
ジェネヴァイブはふたりのうしろに立っている警官のひとりのほうをむいた。「警部補さんのお名前はなんとおっしゃるの?」と、彼女は訊いた。
「テランス・ドノヴァンですだ、むふう」と、マクグローティ警務官はこたえた。
グラソック夫人は多少グロッキーであるように見えたが、それでもまだリングに立っていた。
「滑稽だこと!」彼女は声高にいった。「かれがサンフランシスコのドノヴァン家の一員だったなんてね」
挑戦的に、圧倒するようにマクグローティ警務官を見すえた。
「おっしゃるとおりですだ、むふう」と、かれはいった。「わしゃ、かれがそうじゃないというのを期待してただが――かれをあっちへやるとしますだ」
かれはサランのほうをうなずいて示した。
テランス・ドノヴァンの目はアシュリア人を見た。「どうしてこの男がわたしの息子だとわかったのかね?」と、かれは訊ねた。
サランは躊躇していた。かれは告発してしまっていたことを後悔しているように見えた。かれは非難するように微笑して、肩をすくめ、両手を広げてみせた。
「スリー・ゲイブルズ(3つの切妻屋根)で使用人のひとりがわたしの従者に話したんですよ。わたしはその問題について考えてはいなかった――今夜、あなたが来るまでは本当だとは信じられなかったものでね。それで思い出したんです」
「どうすればきみがわたしの名を知っている、などということがおこるのだね?」テランス・ドノヴァンがたずねた。
サランはあきらかにその質問に当惑していた。かれはその瞬間に自分が失敗したことを感じていたが、修復をはかるには遅すぎた。かれは怒りをぶちまけることでその混乱を覆い隠そうとした。
「どうやってそれを知ったからといって、いったい何が違うというんだ」かれは強調した。「わたしは知っているし、友人を殺した犯人が警部補の息子だからといって逃げおおせるのを許そうとしてないってことだ。わたしはだれか他の警官がこの取り調べを追求することを要求する」
テランス・ドノヴァンはうなずいた。「きみは正しい」と、かれはいった。「もうじきブッショール警部がここに来るだろう――警部の船が来るのを聞いたところだ」
「ばかげたおはなしね」グラソック夫人はいったが、その声は小さかった――彼女は弱っていた。
「わたくしはいつだってあの男を信用したことはなくてよ」彼女は付け加えた。「かれは生まれながらにもっている雰囲気からいってわたくしにこれっぽっちの感銘も与えなかったわ」
そのとき、警部の制服を着た大柄の男が部屋にはいってきた。男はドノヴァン警部補にうなづくと、その横についた。2人の男はしばらくの間低い声でなにやらささやきあっていたが、やがてブッショール警部はジョン・サランに太い人差し指を向けた。
「きみはマックリン・ドノヴァンをメイスン・ソーン殺害の罪で告発するかね?」かれは尋ねた。
「わたしは誰も訴えませんよ」とサランはこたえた。「わたしはただ自分が何を目撃したかを話すだけです」
「ドノヴァン警部補に話したことのほかには、何を目撃したのかね?」
「警察がきたあと、警官たちがソーンさんの死体を下の階に運んでいるあいだにドノヴァンくんはかれの部屋にはいって、ポケットから1枚の紙切れを取り出すとそれを燃やしたんです」
マックリン・ドノヴァンは驚いて話し手のほうをみた。サランは真実を話している、だが、かれはどうやってそれを知ったんだ?
「おそらく」とアシュリア人がつづけた。「かれはそのときにピストルを隠したに違いないんだ――もちろん、かれがソーンさんを撃ったのだとしての話ですが。いまかれがピストルを持ってないとすれば、それはかれの部屋にあるのかもしれない。かれは捜査されるべきだし、かれの部屋もそうされるべきだ」
「だども、そりゃまったくの濡れ衣ですだ」マクグローティ警務官は不平をいった。「わしゃあ、マッキー・ドノヴァンが膝小僧の高さしかなかったころから知ってるだが、そのあたまにゃ卑劣な毛の1本だってありゃせんですだ」かれはグラソック親子にだけ聞こえるような小さな声でささやいた。
「それであなたはかれがそちらの方のご子息だとお認めになるというわけね」
グラソック夫人は非難した。「わたくしは驚いていないわけではなくてよ。あの子が下品な顔をしているのは間違いないといったまでよ」
ジェネヴァイヴ・グラソックは目を大きく見開いた驚きの表情で母親を見た。
「わたしはかれはすばらしいと思いますわ」
と、彼女はいった。「わたしはかれと結婚しようと心を決めています」
彼女は老母がこれまでに持ち込んできた結婚話に対するありがたくない努力に対して、ひとこといい返すという誘惑に抵抗することができなかった。
「あなたはきょうにもフィラデルフィアにお戻りなさい」
グラソック夫人がきつくいった。
ブッショール警部は凶器――それを見つけられなかった――を求めてマックリンを調査していた。
「ではきみの部屋を見せてもらおうか」
かれはいった。「早く来るんだ」
かれはサランを指さした。「きみはここに残って休んでいたまえ。誰も部屋からで来ないか見張っているんだ、マクグローティ」
ドノヴァン警部補はブッショールのともをしてサランやマックリンと一緒に階段へ向かいながら、図書館のまわりをすばやく見まわした。
「執事はどこにいる?」
かれは不意に問うた。
「おや、ちょっと前までここにいたんだが」
パーシィ・ソーンがこたえた。「たぶん隣の部屋にでも行ったんでしょう」
そしてかれは自分の父親の死体が安置されている研究室を示した。「グリーヴズ!」
かれは呼んだが、返事はなかった。
警官のひとりが隣接する部屋に踏み込んだ。「そこには誰もいません」
とかれはいった。
「捜すんだ」
マックリン・ドノヴァンを横に従えて階段を上りながら、警部が指示した。
階段を半分ほど上ったところの左手は背の高いガラスの壁になっていた。それに反射して、まさしくその瞬間、マックリンは薄暗いホールの反対側の端からすばやくかれの部屋に駆け込むひとりの女性の影を見た。家の中の女性すべてがあれを見守って図書館の下にいたという事実がかれの心の中にひらめいたときかれが見ていたことこそが、ブッショールに話すポイントだった。あの影はナリヴァ・サランだった。
それからすぐ、かれらはホール全体をたっぷり見回せる階段の一番上にたどり着いた。だれがかれの部屋に入ろうと、去る機会はないはずだった。ホールは警官たちが来てからかれがそこを通り抜けた最後までずっと照らされていたが、いまは灯りは消されていて、唯一の照明は階段の上の方から来るという状態だった。だれが照明を消したのか、しかもどうやって? もしかするとかれがたったいま鏡に映っているのを見たものがなぜなのかを説明してくれるのかも知れない。
3人の男はまっすぐマックリンの部屋に向かって歩いた。そしてそれは、ホールと同じように暗かった。しかし、ドノヴァンは部屋を出るときに読書机のランプを点けっぱなしにしていたことをはっきりと思いだしていた。ドアのすぐ横にスイッチがあった。マックリンがそのスイッチを押すと、部屋にひかりがあふれた。
「わたしはあなたが徹底的な捜査をすることを提案します」
とサランがいった。
「きみから提案して欲しいと思ったら、わたしのほうからそうしてくれというさ」
ブッショールは簡潔にこたえた。
サランはしかめ面をしてうつむいた。
「銃を持っていたかね、マックリン?」
警部が訊ねた。
「ドレッサーの中にあります――左側の一番上のひきだしです」
若きドノヴァンは親指のすばやい動きで家具の一つを指し示してこたえた。
ブッショール警部は部屋を横切ってドレッサーのところにいくと、左上のひきだしを開いて、その中をしばらくかき回した。
「ここには銃はないぞ、マックリン」とかれはいった。
マックリン・ドノヴァンは両の眉を寄せた。
「ソーンさんが殺されたその瞬間まであったんですよ」とかれはいった。
「ちょうどそこに置いたところだったんです」
警官はドレッサーを探し、さらに2つの部屋とクローゼットの家具類すべてを探し続けた。そのどこでも、かれはピストルを見つけだすことができなかった。サランは最大の困難の中で、きわめて明確に話したいという欲望を抑えていた。ついにかれは長すぎる平穏を我慢しきれなくなった。「ベッドを捜したらどうですか」彼は熱心に要求した。
マックリンはすばやくベッドのほうを見た。最初に注目したベッドの脚のところのカバーは乱れていて、あたかもかれらがもうすでに横から引き抜いていて、あわてて元に戻そうとしたかのようだった。ブッショールは部屋を横切ってベッドに向かうと、カバーをはずして横に置いた。かれはそれらを1枚ずつ取っては振っていた。最後には、かれはスプリングからマットレスを引き剥いだ。サランはもうほとんどつま先立っている状態だった。そこには武器はなかった!
若いほうのドノヴァンは可能な限りサランに注目して見つめていたが、アシュリア人の表情は驚きなどないままに鍵がかけられているように見えた。
ドノヴァンに対する捜査が続いているあいだ中ずっと、かれは部屋の捜索のはじまる前のわずか1分の間に部屋に入っていくのを目撃した人物の発見を待ち続けていた。ありとあらゆる奥まったところや隙間が隠された気配すら明らかにすることなく捜査されていくあいだ、 かれはマットレスの下からピストルが発見されなかったそのとき、それまでサランが示してきたことはまったくもって意外な展開だったという程度までに変わっていた。いくつかの窓のひとつに歩み寄って、かれは注意深くペントハウスの正面沿いの屋根を調べた――そこには誰もいなかった。
グリーヴズを捜索するために派遣されていた警官がちょうど部屋に入ったとき、かれらは図書館にもどってきた。
「わしゃ、この場所全部を捜しましただ、警部さん」
かれはいった。「あいつぁ、ここにゃ、いませんだ。ペントハウスはいつだって外から見張られつづけてますだで、前も、後ろも、だれもいりゃせんですだ、だぁれもでてっちゃいませんですだ」
ブッショールはうなずいた。「ということは犯人は建物の内部にいるはずだ」とかれはいった。かれは室内の仲間のもとへ向かった。「きみたちは今回の事件についてなにか妙なからくりがあることを認めることになるだろう。わたしは嫌疑に基づいてきみたち全員を逮捕することだってできるが、そうはしないつもりだ。いまはだれのことについても問題はないし、わたしはきみたちが朝まで警戒のもとにここに留まるか、駅に向かうかの選択権を与えたいと思う。この状況でわたしは例外を認めることはできないし、わたしが君たちをここに留まらせることの要点をずっと引きのばしている。どちらがいいかね?」
かれらはひとりのこらずこの建物で、警戒のもとに留まることを選んだ。
「自分たちの部屋にもどって、そこにいるんだ」かれは部屋から歩み出てくると、ドノヴァン警部補に自分についてくるよう、合図を送った。「わたしはここからかれらを退散させた」
かれは低い声で説明した。「なぜなら、ここは殺人犯を罠にかけるには最善の場所だからな。犯人はかれらのうちの誰かだが、だれだかはわからない。だれひとりこの建物から出しちゃいかんし、うわさをするのも、呪われた執事を捜すのもダメだ。それでは、8時頃にまたあおう」そしてかれは立ち去った。