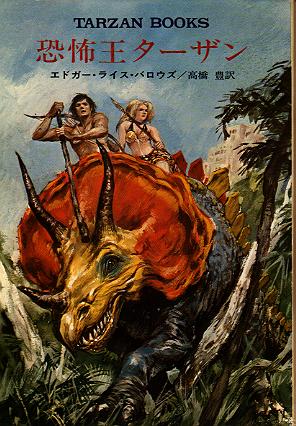 一般庶民が英雄豪傑に対して抱く敬愛、憧恨あるいは哀惜の念が高じると、いわゆる“英雄不滅論”が芽生えてくる。とりもなおさずそれは、悪に対し、あるいは権力(それはしばしば悪と同義である)に対してまったく無力な自分たちにとって代り、不正をただしてくれる救世主への、力弱き庶民のはかなく切ない願望の裏返しでもある。
一般庶民が英雄豪傑に対して抱く敬愛、憧恨あるいは哀惜の念が高じると、いわゆる“英雄不滅論”が芽生えてくる。とりもなおさずそれは、悪に対し、あるいは権力(それはしばしば悪と同義である)に対してまったく無力な自分たちにとって代り、不正をただしてくれる救世主への、力弱き庶民のはかなく切ない願望の裏返しでもある。身近かなところで、あの判官義経が蝦夷から中国大陸に渡ってジンギス汗になったという説や、鎮西八郎為朝が生きのびて琉球王朝の祖となったなどという例がある。これは歴史上に実在の人物だが、フィクションの上で心理的にこれと似た関係にあるのが、コナン・ドイルの創造になる名探偵シャーロック・ホームズと有名なベイカー・ストリート・イレギュラーズの“シャーロキアン”たち、といったらこじつけに過ぎるだろうか。
ターザンに対するファンたちの敬愛や憧憬の想いにも、明らかにこれと同じ心理が介在するといってよい。正真正銘のターザン・ファン(私はシャーロキアンにならって、“ターザニアン”とでも呼びたいが)なら、誰しも一度は「もしこんな魅力的な野生児がほんとにこの世にいたとしたら……狼に育てられた狼少年の実話もあることだし、ひょっとしたらひょっとして?」などとラチもない夢想にふけったことがおありだろう。
その夢想をものの見事に叶えてくれた男がいる。アメリカのSF作家フィリップ・ホセ・ファーマーである。誰よりも熱烈なターザン・ファンをもって認ずる彼は、ターザンよ生きてあれと願う一人で、とうとう本物のターザンを探しあてたと名乗りをあげたのだ。その努力の成果がこのほど、『実在するターザン――グレイストーク卿の決定的伝記』 Tarzan Alive:a definitive of Lord Greystoke と題する一冊の本にまとめられて、アメリカのダブルデイ社から出版された。
この本は、表紙から裏表紙、索引のたぐいに至るまで、徹頭徹尾「ターザンは実在の人物」という架空の事実(!)にもとづいて構成されている。まず献辞からしてこうだ。
「本書を、真実の“グレイストーク卿”である男に、また、虚構をよそおってとはいいながら、彼に衆目を集めさせた男に捧げる」
つづいて前文もふるっている。
「本書は、実在の人物の伝記である。したがって図書館や書店では、『B』(伝記 biography の頭文宇)の棚に置かれるべきである。また索引力−ドには、「グレイストーク卿の生涯(1888年〜1946年)」と記入さるべきである。
ある人は、この本が実在のターザンの身元調査を兼ねているところから『ミステリー』の分類に入れてもいいのではないか、と異議を申し立てるかもしれない。また他の人は、これは小説家の書いたセミフィクショナルなシリーズに準拠しているのだから『フィクション』の項目に入れるぺきだ、と反論するかもしれない。しかしながら本書は、“グレイスト―ク卿”に関するパロウズの著作の中で彼が書き落した欠落部分の補填と、一見矛盾して見える部分の解明とを、真剣に試み、その著作から、虚構であり不可能であり有り得ない個所を削除せんとするものである。
かくして最後に残った部分こそは、私の信ずるに、いまはおそらく絶滅したであろう世にもまれな猿人一族とともに青春時代を送った、一人の真に実在する英国人の生涯と事件とを、かなりの程度まで正確に伝えることになろう……」
さらにファーマーは本文冒頭で、アフリカのジャングルで猿人に育てられた不思議な男の話を、いかなる奇縁で聞き知り、小説の形で発表することになったかを、次のように述べる。
「もしこの世にワインが存在しなかったら、われわれはこのオデッセイ以来もっとも有名な冒険家、もしくはサムソン以来最強の男の物語を、ついに知ることがなかっただろう。
アメリカの小説家エドガー・ライス・バロウズは1911年冬のある夕、英国植民省のある追職官吏から晩餐に招かれた。役人はかなり酒杯を重ねたが、パロウズは控え目に飲んだ。翌日、彼は“英国人”の話をはっきりと思い出した。
招待主はバロウズの懐疑的な態度にプライドをいたく傷つけられながらも、植民省のファィルから、自分の世にも不思議な物語を“証明”する古い記録と、だいぶ昔に死んだある男の日記とを探しだした。
なかば本気になったパロウズは、手にはいったあらゆる記録をひっくり返して調べた。自分の読んだものに触発されて、彼は大体において事実に忠実な伝記を書いた。だが、そこここに現われた欠落部分は、推量をもって補わなければならなかった。推量のうちには的に近かったものもあるし、完全な見当違いに終わったものもあった。伝記はまず、オ―ルスト―リイ・マガジン誌1912年10月号に、『類猿人タ―ザン』と題して発表された。ただこの伝記は完全なフィクションとして世に出されたので、バロウズは収録の要なしと判断した部分をたくさん切り捨てた。そのようなギャップを補い、謎めいた部分や矛盾めいて見える個所を訂正ないし解明することが、この“実説タ―ザン”の目的である。(以下略)』
もう一つ、本書の謝辞の中で、ファーマーは喜々として、隠遁生活を送る本物のターザンの所在を苦心のすえにつきとめ、ついに赤道直下は西アフリカ、ガボンのリバーヴィルにある某ホテルで、写真もテープもいっさい取らぬという条件のもとに、15分間のインタビューに成功したことを報告する。
「……残念なことに、私はその貴重なインタビュー時間の三分の一ほどを、いっぺんにつづけてというわけではないが、ただただ彼に見惚れることに費やしてしまった。私はいままで、これほど美しい、だが同時にこれほど否定の余地なくたくましい男に出合ったことがなかった。パロウズが語ったひたいや首の傷跡や、バロウズも言及しなかったもっと数多くの顔や手の傷があるにもかかわらず、そうなのだ。彼が口を開かぬときでさえ発散している並はずれた精神力に圧倒されて、私は沈黙した。猛々しい、という表現のほうが、おそらくもっと適切だろう。何かが、彼の中でぎらぎらと燃えているのだ。
彼が私と同じように血を流し、死ぬこともある生身の人間だ、と百も承知の上でなお私はいま不死身の男の前にいるのだという気がしてならなかった。彼がそのとき80歳という齢でありながら、どう見てもせいぜい35かそこらにしか見えなかったという事実は、彼と同席していないいまとなっては、信じがたいことのように思える……」
タ―ザンがなぜにかくも若々しいのか、という理由も、ファーマーはちゃんと用意している。
それによれば、1912年1月、ウガンダでライオンに襲われた原住民のまじない師を助け、お礼に“不老不死の薬”を飲まされ、薬の効き目についてはタ―ザン自身も半信半疑だったが、以来彼の老化のテンポは極端にのろくなり、今もなお外見的には青年の若さを保っている、というのである。
この伝記の中で、さらにもう一つ、読者をウレシクさせる部分は、タ―ザンの家系を8代前まで綿密に調べあげたところ、なんとこの男が、前記のホームズはもちろん、“紅はこペ”ことパーシー・ブレ―クニィ卿や“ドク・サヴェッジ”ことウィリアム・ハーパー・リトルジョン、名探偵ネロ・ウルフやピーター・ウィムゼイ卿、さらに快男児“ブルドッグ”ドラモンドなどなど、大衆文学史上に名を残す有名人たちとさまざまな血縁関係にあることが判明した、というところである。
ファーマーはここでさすがにSF作家らしく、ターザンの一族にかくも知力体力衆に秀でた人物たちがなぜ輩出したのか、その原因を1975年イギリスに落ちた隕石の放射能によるミューテーション(突然変異)に求めているのだが、ここでは紙数の関係もあるため詳しいことは省かせていただく。といってもご安心、この“実説タ―ザン”伝の版権は当社が獲得できたので、いずれ本シリーズの別巻として刊行することに決まった。それまで楽しみに待っていただきたい。
なお、本書のアメリカ版の末尾に、バロウズ自身がターザンからノートを借りて作ったという、『パル・ウル・ドン主要語解説』がついているので、ご参考までに添付しておく。あんがい、こうした作者の“遊び”にヒントを得て、ファーマーも“実説ターザン”伝を書く気をおこしたのかもしれない。