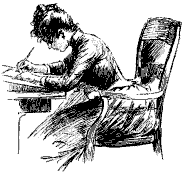
CHAPTER I / 第1章
e-txt:長田秀樹
翻訳:長田秀樹
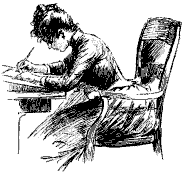
| The closed door of the bedroom opened. A
bent and white-haired old Negro walked
slowly
out, his face buried in a red bandanna
and
his shrunken shoulders heaving to the
sobs
he could not control. Down at the Negroes'
quarters the banjoes and the old melodeon
were stilled. Even the little children
sat
with hushed voices and tearful mien.
In the
big front bedroom of the mansion two
women
knelt beside a bed, their faces buried
in
the coverlet, weeping. There were tears,
too, in the eyes of the old doctor,
and even
stern old Judge Sperry blew his great
beak
of a nose with unnecessary vigor as
he walked
to the window and looked out across
the broad
acres of his lifetime friend. Jefferson
Scott
was dead. That night Scott Taylor, the son of Jefferson Scott's dead sister, arrived from New York. Virginia Scott had met him several times in the past, when a child, he had visited his uncle. She knew but little of his past life, other than that Jefferson Scott had paid on two occasions to keep him out of jail and that of recent years the old man had refused to have anything whatever to do with his nephew. Taylor was a couple of years her senior, a rather good looking man, notwithstanding the marks of dissipation that marred his features. He was college bred, suave and distinctly at ease in any company. Had she known less of him Virginia Scott might easily have esteemed him highly, but, knowing what she did, she felt only disgust for him. His coming at this time she looked upon as little less than brazen effrontery, for he had been forbidden the house by Jefferson Scott several years before, nor since then had he once communicated with his uncle. That he had returned now in hope of legacy she knew as well as though he had candidly announced the fact, and it was with difficulty that she accorded him even the scantest courtesy in her greeting. Judge Sperry, who was searching among Jefferson Scott's papers in the library when Taylor arrived, took one look at him over the tops of his glasses, a look that passed slowly from his face down to his boots, ignoring his proffered hand and returned to his search without a further acknowledgement of the younger man's existence. Taylor flushed, shrugged his shoulders and turned back to Virginia, but Virginia had left the room. He fidgeted about, his ease of manner a trifle jarred, for a moment or two, and then recovering his poise, addressed Judge Sperry. "Did my uncle leave a will?" he asked. "He made a will, sir," snapped the Judge, "about a year ago, sir, in which you were not mentioned, sir. He has made no other, that I know of. If I were you, sir, I should return to New York. There is nothing here for you." Taylor half smiled. "I take it you are looking for the will," he said. "Well, I'll just stick around until you find it. If you don't find it I inherit half the property -- whether you want me to or not." Judge Sperry vouchsafed no reply, and presently Taylor left the room, wandered out across the grounds and down the road toward the little village, where, if there were no acquaintances, there was at least something to drink. Later in the evening, fortified by several Kentucky bourbons, he returned, nor could Virginia's mother bring herself to refuse him the ordinary hospitalities of that old Virginian home, and so he remained, following the body of his uncle to the grave with the other members of the family, the friends and the servants. And after the funeral he stayed on, watching with as eager eyes as the rest the futile search for the last will and testament of Jefferson Scott, but with homes diametrically at variance with theirs. Naturally he saw much of Virginia, though not as much as he should have liked to see. He found that the little girl he had known years before had grown into a beautiful young woman and while it angered him to realize the contempt in which she held him, he was not so wanting in egotism but that he believed he might win his way eventually into her good graces. For this reason he never reverted to the subject of the will. It had been Jefferson Scott's intention that Virginia should inherit his entire estate they both knew, and were equally positive that the administrators would adopt every legal means to carry out the grandfather's expressed wish. Judge Sperry had explained Taylor's legal rights in the event that no will should be discovered, nor was Virginia at all desirous of attempting to reduce the amount that might be legally his. It was the evening before the meeting. Taylor had gone to town in the afternoon. Mrs. Scott had already retired and Virginia sat reading in the library when Scott Taylor entered. As the girl greeted him civilly her eyes took in his flushed face and unsteady carriage and she saw that he had been drinking more than usually. Then she let her eyes fall again to her book. "Look here, Virginia," he said, leaning forward toward her unsteadily. "Yes?" The rising inflection was accompanied by a raising of the arched brows. "Why not be friends, Virginia?" Taylor continued. "We're both of us due for a share of the old man's property. It amounts to a big bunch of coin, but it's mostly in farm lands. It ought not to be cut up. We ought to keep it intact. I got a scheme." He edged his chair closer until their knees all but touched. "We're about the same age. I'm not such a bad sort when you know me, and you're a peach. I always knew it and this time I've discovered something else -- I love you." He was leaning so far forward now that his face was close to hers. "I would not, for the world," she said, "intentionally wound any man who came to me with an avowal of honest love; but I do not believe that you love me, and, further, the manner of your coming to me is an insult." "You can learn to love me," he muttered, and seized her in his arms. Virginia struggled, but he crushed her closer to him until his lips were above hers. With an effort almost superhuman the girl succeeded in covering Taylor's face with her open palm and pushing him from her. Unsteady from drink, the man staggered back against the chair he had left, toppled over it and fell in a heap upon the floor. When, after an effort, he managed to crawl to his feet, Virginia had disappeared. Taylor sank to the edge of a chair, his face contorted with rage and humiliation. He was not so intoxicated but that he now realized the fool he had made of himself and the ridiculous figure he must have cut reeling drunkenly over the chair. His rage, instead of being directed against himself as it should have been, was all for Virginia. He would make her pay! He would have his revenge. She should be left penniless, if there was any way, straight or crooked, to accomplish it. And in this pleasant mood Scott Taylor made his unsteady way to bed. It was late when Taylor awoke the following morning. Already the administrators had gathered with Mrs. Scott and Virginia in the library. It was several minutes before the man could recall to memory the events of the previous evening. As they filtered slowly through his befogged brain a slow flush of anger crept over his face. Then he recalled the meeting that had been scheduled for today. He glanced at his watch. It was already past time. Springing up he dressed hastily, and left his room. Half way down the stairs he heard voices coming from the library below. He paused to listen. Judge Sperry was speaking. "Jefferson Scott never intended that that young scalawag should have one cent's worth of his property," he was saying. "He told me upon several occasions that he would not have his money dissipated in riotous living, and by gad, gentlemen, if I have anything to say about it Jefferson Scott's wishes shall be observed," and he pounded the black walnut table with a heavy fist. "I think," spoke up another voice, "that when the simple proofs necessary to establish legally Miss Virginia's relationship to General Scott have been produced it will be a comparatively simple matter to arrange the thing as he would have wished it." A moment later he entered the library. His manner was easy and confident. He sneered just a little as Virginia deliberately turned her shoulder toward him. A vast silence fell upon the company as he joined them. He was the first to break it. "I am glad," he said, "that we can now straighten out a few matters that have been causing several of you not a little annoyance." He glanced defiantly at Judge Sperry. "Jefferson Scott, my uncle, died intestate. Under the circumstances, and the law, I inherit -- I am the sole heir." Mrs. Scott and the administrators looked at the young man in surprise -- Virginia kept her back toward him. For several seconds there was unbroken silence -- the bald effrontery of Taylor's statement had taken even Judge Sperry's breath away -- but not for long. "Sole heir?" shouted the old man presently. "Sole heir? Sole nothing! You don't deserve a penny of your uncle's estate, and you don't get a penny of it, if I can prevent it." "But you can't prevent it, my friend," Taylor assured him coolly. "You can't prevent it because, as I just said, I am the sole heir." "I presume," bellowed the Judge, "that you have more rights here than General Scott's granddaughter?" "He had no legitimate granddaughter," replied Taylor, the sneering laugh on his lips speaking more truly the purport of his insinuation than even the plain words he had used. "What? You young scoundrel!" cried Judge Sperry, springing to his feet and taking a step toward Taylor. "Don't get excited," said Taylor. "Of course it's unfortunate that it became necessary to touch upon this matter, but I gave Miss Virginia an opportunity to compromise last night, which she refused, and so there is nothing else for me to do but insist upon my rights. It's a very simple matter to rectify if I am not mistaken. All that Mrs. Scott need do is produce her marriage certificate, or the records of the local authorities where her wedding took place. And now, until she can establish the right of her daughter to make any legal claim whatsoever upon the estate of my uncle, I shall have to ask you all to vacate the premises and leave me in possession of what is mine and no one else's." The administrators turned toward Mrs. Scott. She shook her head sadly. "You all know, of course, as well as he does, that his charges are as false as they are infamous," she said. "I was married in the heart of Central Africa. Whatever records there were of the ceremony have long since been destroyed, I fear; and I fear also that it may be a difficult thing to legally prove my marriage. Robert Gordon of New York was one of the witnesses. If he still lives I presume an affidavit from him would be sufficient?" She glanced at Judge Sperry. "It would," he assured her, "and in the meantime I intend to kick this miserable little puppy into the road." And he advanced upon Taylor. It was Mrs. Scott who stepped in front of the Judge. "No, my dear friend," she said, "we must not do that. He has, possibly, legal if not moral right upon his side, for until I can prove the legality of my marriage he is in the eyes of the law the sole heir. And in the meantime Virginia and I shall make our preparations and leave here as quickly as possible." "You will do nothing of the sort," exploded the Judge. "You will stay right here. If you leave it will be a tacit admission of the truth of a lie. I won't hear of your leaving, not for a moment. If anyone leaves, this rascally blackleg will be the one to go." "No," spoke up Virginia. "I shall not leave. The Judge is right." "As you will," said Taylor. "I can't kick a couple of women out of my home if they insist on remaining." "You'd better not," growled the Judge. It was not until afternoon that Mrs. Scott found an opportunity to pen a note to Robert Gordon. She had not seen her husband's old friend since that day twenty-one years before that she had waved him farewell from the veranda of the bungalow within the palisade of her mission home. He had stopped in London on his way to America, met and married an English girl, and thereafter for long years had spent much time in England or in travel. It had not been until after the death of his wife that he had returned to New York permanently. As Mrs. Scott finished the letter an automobile whirled up the driveway and came to a stop before the mansion. Women's voices floated in to her and to Virginia to whom she had been reading the completed letter. The latter walked over to the open doors, where she glanced out, and then, turning to her mother with an "Oh, it's Mrs. Clayton and Charlotte!" ran out to greet visitors. Mrs. Scott, as thoroughly imbued with Southern hospitality as a native daughter, dropped her letter upon the desk and followed Virginia to the porch, where she found her friends insisting that she and Virginia accompany them on a drive to the village. As it was too warm for wraps neither mother nor daughter returned to the house, and, only too glad of an interruption to the sorrows and worries that had recently overwhelmed them, entered the machine of the Clayton's and a moment later were whirling down the road in a cloud of dust. Scott Taylor, who had been strolling about the plantation, returned to the house shortly after they had left and entering through the French windows of the library, chanced to note the open letter lying on the desk. It required no subjugation of ethical scruples upon his part to pick the letter up and read it. The letter ran: My dear Mr. Gordon: My husband's father, Jefferson Scott, has just passed away, and as certain legal requirements necessitate a proof of my marriage to Jefferson I am writing to ask that you mail an affidavit to Judge Sperry, of this village, to the effect that you witnessed the ceremony. "My marriage certificate is, I imagine, still in the tin box beneath the hearth of the mission bungalow where father always kept his valuables, but as even it may have been destroyed during the second uprising of the Wakandas I imagine that we shall have to depend entirely upon your affidavit. I understand that the savages left no stone standing upon another, and that every stick or timber was burned. That was eighteen years ago -- a year after the massacre in which Jefferson, father and mother were slain, and so it is rather doubtful if anything remains of the certificate. "I am particularly anxious to legally establish the authenticity of my marriage, not so much because of the property which my daughter Virginia will inherit thereby, as from the fact that another heir has questioned my daughters legitimacy. "I write thus plainly to you because of the love I know that you and Jefferson felt for one another, as well as to impress upon you my urgent need of this affidavit, which you alone can furnish. Very sincerely. RUTH MORTON SCOTT Scottsville, Va. July 10, 19 ." "H'm," commented Mr. Scott Taylor, with a laugh. "Well, I can let this letter go forward with perfect safety, as I happen to know that Robert Gordon, Esq., died two years ago." |
寝室の閉ざされていたドアが開いた。腰の曲がった白髪の年老いた黒人はゆっくりと立ち去った。その顔は赤いバンダナに埋まり、そのしなびた肩がむせび泣きとともに上下することをかれはおさえきれなかった。黒人居住区の下町ではバンジョーも古びたメロディオン(訳註:アコーディオンの一種)も音をなくしていた。小さな子供たちでさえ小声になり、涙ぐんだ様子で座り込んでいた。邸宅の寝室の大前ではふたりの女性がベッドのそばにひざまずいており、その顔をベッドカバーにうずめて、泣いていた。高齢の医師の目にも涙があり、厳格な老スペリー判事でさえ窓にむけて歩き、またかれの終生の友人の遺した広大な敷地を見渡しながら、その大きな鼻の先を不必要なまでに激しくすすっていた。ジェファースン・スコットは死んだのだ。 その夜、ジェファースン・スコットのすでに亡くなっていた妹の息子であるスコット・テイラーがニューヨークから到着した。ヴァージニア・スコットはそれまでも何度かかれにあったことがあった。子供のころ、かれは自分の叔父を訪ねてきていたものだった。彼女は、ジェファースン・スコットがかれを留置所から保釈させるための費用を払ったのが2回、最近は甥のためにどうこうすることはなんであれ断っていたこと、それ以外にはかれのそれまでの生活についてはほとんど何も知らなかった。 テイラーは彼女より2年ばかり年長で、どちらかといえば見栄えのいい男だったが、それにもかかわらずその容貌を台無しにする浪費癖だった。かれは大学を出ていて、慇懃で、だれと接するときでもまったく落ち着き払っていた。もし彼女がかれのことをそんなに知らなかったら、ヴァージニア・スコットは簡単にかれのことを高く評価してしまっていたかもしれない。しかし、彼女はこれまでのことを知っていたので、かれについては嫌悪感しか感じなかった。何年か前にジェファースン・スコットに家に来ることを禁じられたかれの今回の来訪には図々しい厚かましさを感じないわけにはいかなかった。それ以来、ただの一度だっておじさんに連絡さえ寄こさなかったというのに。かれが遺産を期待して帰ってきたということは、あからさまにそう宣言しているのと同じくらい、彼女にはよくわかっていた。そして、彼女の挨拶に対して十分とはいえない礼儀さえかわすことは困難なのだということもわかっていた。 テイラーが到着したとき書斎のジェファースン・スコットの書類の中を捜していたスペリー判事は、めがねの上ごしにかれを見つけてそれを受け取ると、かれの頭の先からつま先までゆっくりと見渡し、かれのさしだした手を無視して若者の存在に関する証明書を無視して自分の調査に戻った。 テイラーは顔を真っ赤にすると、肩をすくめてヴァージニアのほうに振り返ったが、ヴァージニアは部屋を出ていったあとだった。かれはそのあたりでそわそわして、つまらないことで動揺したかれの態度は一瞬か二瞬で平穏を取り戻し、身のこなしを整えると、スペリー判事に申し込んだ。 「叔父さんは遺言を残しましたか?」とかれは尋ねた。 「かれは遺言をつくりましたよ、サー」判事はがみがみといった。「1年ほど前でしたかな、サー、あんたについての言及はありませんでしたな、サー。わしが知る限りではかれは他にはつくっておりませんな。もしわしがあんただったら、サー、とっととニューヨークに帰るでしょうな。ここにはあんたのものはなんにもないんじゃ」 テイラーは半ば笑っていた。 「あなたが捜している遺言を見せてもらいますよ」とかれ。「いいでしょう、あなたがそれを見つけるまではそこいらでじっとしてますよ。もしあなたがそれを見つけられなかったら、ぼくは財産の半分を相続する――あなたがぼくに渡したいとおもっているかどうかは関係なくね」 スペリー判事は返事を返さなかった。やがてテイラーは部屋を出ると、うろうろと歩き回りながら地面を横切り、小さな村に通じる道におりた。そこならば顔なじみがいなかったとしても、せめて酒ぐらいはあるだろう。 その晩遅く、数杯のケンタッキー・バーボンに元気づけられて、かれは帰ってきたが、ヴァージニアの母親もまたかれをヴァージニア州の旧家におけるふつうのもてなしで応じることを断固として断ることはできなかった。そして、そのためかれはとどまり、かれの叔父の遺体を家族のほかの顔ぶれや友人、使用人たちと一緒に埋葬するのに従った。 そして葬儀のあともかれはとどまり、ジェファースン・スコットの最期の遺書か遺言の無益な捜索の手を休めるようすを熱心な視線で見つめていたが、家の中でのそれは、それらのとはまったく異なるものだった。もちろん、かれはヴァージニアに何度も会っていた、とはいえ、会うことを好ましく思っていたことが何度もあったわけではなかった。かれは何年も前から知っていた幼い少女が美しい若い女性へと成長したことに気づいたが、にもかかわらず彼女がかれを軽蔑し続けているという事実がかれに怒りをおぼえさせた。かれはうぬぼれを持たない人間ではなかったが、彼女のすばらしい魅力を最終的には勝ち取れるだろうと確信していた。そのため、かれは遺言の主題に戻ることは決してなかった。 ジェファースン・スコットの意志がずっとヴァージニアがかれの全財産を相続すべきだという点にあったことはふたりとも知っていたが、管理者たちが祖父の明記された希望を実行するためのあらゆる法的手段を採用するであろうことも同様に明らかだった。スペリー判事は遺言が発見されなかった場合のテイラーの法的権利を説明し、同様にヴァージニアは法的にかれのものであるかもしれない金額を減額しようとすることを望んでいたわけではなかった。 会合の前に夕方になっていた。テイラーは昼のうちに街に行ってしまっていた。スコット夫人はすでに退席していて、スコット・テイラーが入ってきたとき、ヴァージニアは書斎ですわって本を読んでいた。娘は礼儀正しくかれに挨拶すると同時に、かれの顔が赤くなっていることと不安定な動作をしていることをその目でとらえた、そして彼女はかれがいつも以上に酒を飲んでいることを見て取った。それから彼女は再び読みかけの本にその視線を落とした。 「こっちを向くんだ、ヴァージニア」とかれは、よたよたと足もとをふらつかせながら、彼女のほうをむいていった。 「はい?」語調があがるのと一緒に、そのアーチ型の眉もあがった。 「なぜ友だちになってくれないんだい、ヴァージニア?」テイラーは続けた。「ぼくらはふたりでご老人の財産を受け取ることになってる。そいつは膨大な金額になるはずさ、でもそのほとんどは農地だ。そいつは細かく切り刻まれるべきじゃない。ぼくらはそいつを完全なままにしておくべきだ。ぼくは名案を思いついた」かれはじわじわと椅子を動かすと、ふたりの膝がほとんど触れそうになるまでその間隔を狭めた。「ぼくらはほぼ同世代だ。きみも知ってるようにぼくはそう悪いタイプじゃないし、きみはかわいこちゃんだ。ぼくはずっとそう思ってきたが、いまもっと別のことに気がついたんだよ――ぼくはきみを愛している」かれは彼女の顔に触れそうになるまで自分の顔を前につきだした。 「わたくしはそうするつもりはございませんわ、天地天命にかけて」と彼女はいった。「真実の恋を認めてわたくしのもとにいらっしゃ殿方ならばたとえどなたであろうと故意に傷つけるようなまねをするつもりはございません――でも、わたくしはあなたがわたくしのことを愛しているなどとは信じられませんわ、それに、あなたがわたくしのもとにいらっしゃるその態度は侮辱的ですことよ」 「きみはぼくを愛することを覚えられるさ」かれはぶつぶついうと、その腕に彼女を抱きしめた。ヴァージニアは抵抗したが、かれはその抵抗ごと押しつぶすと、唇が彼女に触れるほどに抱きしめた。ほとんど超人的な努力によって、娘はテイラーの顔に手のひらを押さえつけ、自分からかれを押し離すことにることに成功した。酔っぱらってふらふらしたまま、男は自分が座っていた椅子までよろよろと後ずさると、そのうえを越えて倒れ、床の上に山になって落ちていた。 努力の末になんとか自分を立ち上がらせたとき、ヴァージニアの姿はすでになかった。テイラーは怒りと恥辱にその顔をゆがめながら椅子の端に沈み込んだ。かれはもうそんなに酔ってはいなかったが、そのとき、自分がいかに愚か者であったか、そしてかれが消し去らねばならない椅子の上の千鳥足の酔っぱらいのバカげた姿を実感していた。かれの怒りは、当然そうであるべき自分自身のほうに向かうかわりに、すべてはヴァージニアにむけられた。あの女に償わせる! かれは復讐を誓った。あの女は無一文になるべきなのだ、そのためにはどんな手段だって、正当なものであろうと不正なものであろうと実行してやる。そしてその愉快な気分のまま、スコット・テイラーはおぼつかない足取りでベッドに向かった。 翌朝、テイラーが目覚めたのはもう遅い時間だった。すでに管理者たちはスコット夫人とヴァージニアを書斎に集めていた。男が昨晩のできごとに関する記憶を呼び起こすまでに数分を要した。それらがかれのぼやけた頭の中をゆっくりと通っていくにつれ、怒りはその顔中に徐々に広がっていった。そして、かれはきょう予定されていた会合を思い出した。かれは腕時計を見た。すでに時間は過ぎていた。かれは飛び起きると、急いで着替え、部屋を出た。階段の半ばまで降りたところで、かれは階下の書斎から漏れてくる声を聞いた。かれは耳をすませて立ち止まった。スペリー判事が話していた。 「ジェファースン・スコットはあの若いやくざ者には財産の1セントだって相続する値打ちはないと考えていたに違いないんじゃ」とかれはいっていた。「かれはわしにろいろな場所で放埒な生活に、そして遊び歩いたりするようなことに無駄遣いするような金は持たないのだと語ったものじゃった、紳士がた、わしはそのことについていえる何ごとかがあるのなら、ジェファースン・スコットの願いは守られるようにするつもりじゃ」 「ぼくが思うに」と、別の声が無遠慮に割って入った。「法的にミス・ヴァージニアがスコット将軍の親族だと確定するのに必要な簡単な証拠がでてきていれば、そのときはかれがそれを望んでいたということを証明するのは比較的簡単な問題だったということになるんでしょうがね」 間をおかずにかれは書斎に入ってきた。その態度は気楽そうで自信に満ちていた。ヴァージニアが故意にかれに背を向けると、かれはかすかな嘲笑を浮かべた。かれが加わったことで一同のあいだに大いなる沈黙が横たわった。最初にその沈黙を破ったのはかれだった。 「ぼくはうれしいね」とかれはいった。「ぼくらが今まさに、あなたにとって少しの迷惑ごとも引き起こすこともなくいくつかの問題を解決できるということがさ」かれはスペリー判事を挑戦的に一瞥した。「ぼくの叔父、ジェファースン・スコットは遺言を残さずに死んだ。この事態においては、そして法律上では、ぼくが相続することになる――ぼくが唯一の相続人なんだ」 ミセス・スコットと管理者たちはその若い男を驚きの眼で見つめた――ヴァージニアはかれに背を向けたままだった。数秒のあいだ、沈黙が横たわった――テイラーが語ったあからさまな厚かましさがスペリー判事に息をのませていたあいだ――しかしそれは長時間ではなかった。 「唯一の相続人?」やがて老人は大声を上げた。「唯一の相続人じゃと? 唯一などということはない! おまえさんは叔父の財産のうちの1ペニーだって受け取るに値しないのじゃぞ、わしが反対できれば、おまえさんは1ペニーだって受け取れやしないんじゃ」 「でもあなたは反対できないんです、ご友人」テイラーはクールにかれに保証した。「あなたは反対できないんですよ、なぜなら、つい今しがたぼくがいったように、ぼくこそが唯一の相続人だからです」 「よかろう」判事は怒号した。「おまえさんがここにいるスコット将軍の孫娘よりも正当な権利を持っているというのならな?」 「かれには法律上、孫娘なんかいなかったんですよ」テイラーは答えた。口元に浮かぶ嘲笑が、かれが使った平易な言葉より以上にそのほのめかしの意味を正確に語っていた。 「なんじゃと? この悪党の若造が!」スペリー判事はバッと跳ね上がると、テイラーのほうに駆け寄りながら叫んだ。 「まあそう興奮しないで」とテイラー。「もちろん、この問題に触れなければならなくなったことは不幸なことですが、ぼくは昨晩、ミス・ヴァージニアに和解の機会をご提示申し上げたんですが、お嬢さんが断ったもので、ぼくは自分の正当な権利を主張するしかなくなったというわけなんですよ。ぼくの誤解でなければ、修正するのは非常に簡単な問題なんですがね。ミセス・スコットがしなければならないのは、ご自分の結婚証明書か結婚された土地の現地官庁の記録を提示するということだけなんですが。いまのところ、彼女はご自分の娘さんがぼくの叔父の財産に関してほんのちょっぴりでも法的に要求できるようになる権利を確立できるまでは、ぼくはあなたに、前提を取り消して、ぼくのものであってそのほかのだれのものでもない財産をぼくに引き渡すことのすべてを求めなければならないでしょうね」 管理人はミセス・スコットのほうに向き直った。彼女は哀しげに頭を振っていた。 「かれの要求がそれらが理不尽なのと同じように間違っているということは、もちろんあなたもかれと同様にご存じのはずですわ」と彼女はいった。「わたくしは中央アフリカの奥深くで結婚しました。破滅が起こってから長い時が過ぎていますから、結婚式に関するさまざまな記録が残っているかどうか、わたくしは恐れています――わたくしの結婚を法的に証明することが非常に難しいかもしれないことも恐れています。ニューヨークのロバート・ゴードンは証人のひとりですわ。かれがまだ生きていれば、かれの宣誓供述書で十分ではないかと期待いたしますけれど?」彼女はスペリー判事を見やった。 「十分じゃろう」かれは保証した。「そしてわしは、当分のあいだ、このケチな小者の犬コロを道ばたに蹴転がしてやるつもりじゃ」そしてかれはテイラーに向かって前進した。 判事の前にミセス・スコットが歩み出た。 「いけませんわ、親愛なる判事さま」彼女はいった。「わたくしたちはそんなことをしてはなりません。かれは、もしかすると、道徳的には正しくないかもしれませんけれど法的な権利は持っているのですわ、わたくしの結婚を証明できるまでのあいだは、かれは法の眼が認めた唯一の相続人なのですわ。そしてもう一方のヴァージニアとわたくしは出きる限り早くに準備をしてここを立ち去るべきなのでしょう」 「あんたはそういったことは何一つせんでいいんじゃ」判事は喝破した。「あんたはここに正当に居続ければいい。もしあんたが出ていったら、うそつきの道理を暗黙のうちに了解したことになってしまう。わしはあんたが去るなどということに耳は貸さん、ほんの一瞬だってな。もしだれかが立ち去るというなら、このごろつきの詐欺師がいくことになるじゃろう」 「ええ」ヴァージニアは声をあげた。「わたくしは立ち去りません。判事さまが正しいわ」 「そうまでおっしゃるというなら」とテイラーはいった。「ぼくの家に居続けたいというおふたりのご婦人を蹴り出すなどという真似はいたしかねますが」 「おまえさんはそうせんほうがいいじゃろうな」判事はうなり声を上げた。 午後になる前にミセス・スコットはロバート・ゴードンへの覚え書きをしたためる機会を見いだした。彼女は布教所の住まいのある防護柵の内側のバンガローのベランダから手を振って別れて以来21年間、夫の旧友とはずっと会っていなかった。かれはアメリカへの帰路にロンドンに滞在し、イギリス人の女性と出会って結婚し、それ以来何年もの年月をイギリスで過ごすか旅をすることに費やしていた。かれの妻が亡くなったのちまで、かれはニューヨークに長期間戻ることはなかったのだ。 ちょうどミセス・スコットが手紙を書き上げたとき、1台の自動車が車道を上がってきて、邸宅の前でとまった。何人かの女性の声が、彼女とできあがった手紙を読み聞かせていたヴァージニアの耳に届いた。ヴァージニアが出ていくと外をうかがいながらドアを開け、それから母親に向かって「まあ、ミセス・クレイトンとシャーロットだわ」というと、訪問客に挨拶するために出ていった。 この土地で産まれ育った娘同様に南部風の歓待が徹底して染みついていたミセス・スコットは手紙を机におくと、ヴァージニアを追ってポーチに出て、そこで友人たちが彼女とヴァージニアに村へのドライブにいっしょに行きましょうと誘っていることを知った。それは家に帰ってきた母親でも娘でもないふたりをとても暖かく包むものであり、そして、最近ふたりをまいらせていた悲しみや悩みを中断させることは大きな喜びでもあったので、クレイトン家の車に乗り込むと、すぐさま砂ぼこりを舞あげながら道をらせん状に下っていった。 農園をぶらぶら散歩していたスコット・テイラーはすばやくふたりが出ていった家に戻ると、書斎のフランス窓を通って中に入り込み、開かれたまま机の上に置かれていた書きかけの手紙を手にする機会を得た。かれはその手紙を取り上げて読むことに道徳的な良心のとがめと闘う必要は一片たりとなかった。 手紙はこう書かれていた―― 「親愛なるゴードンさま わたくしの夫の父親であるジェファースン・スコットは今しがた他界いたしました。そこでジェファースンとわたくしとの結婚に関する疑う余地のない法的な資格を持った証拠書類が必要となったため、わたくしはあなたに、当村在住のスペリー判事あてにあなたが結婚式の証人であるという主旨の宣誓供述書を届けていただきたく、お願いするためにこの手紙を書いております。 わたくしの結婚証明書は、わたくしが思いますところ、父が貴重なものは常にそこにおくと決めていた布教所のバンガローのいろりの下のスズの箱の中にまだあるかとおもわれますが、ワカンダ族の2度目の反乱のあいだに破壊されてしまったかもしれず、わたくしとしてはあなたの宣誓供述書に頼るしかないものと考えております。わたくしには蛮人たちは一石さえも同じところに立ったままにはしておかず、すべての棒や木材は燃やしてしまったと考えています。それは18年前のことでございました――父と母いずれのジェファースンも殺された大虐殺の1年後、そうどちらかといえば証明の遺跡のようなものでしたから、より正確にはその疑いがある、ということでございますが。 わたくしはわたくしの結婚が確かなものであったことを法的に立証することをことさらに切望しております。わたくしの娘のヴァージニアが相続するはずの膨大な財産のためではなく、もうひとりの相続人がわたくしの娘の合法性を疑っているという事実からです。 あなたとジェファースンが互いに感じていたことがわたくしにはわかっている愛情のために、またそれと同様にあなただけが提供して下さることのできるこの宣誓供述書をわたくしが緊急に必要としているということをあなたに間違いなくお伝えするために、わたくしはあなたにこのような飾り気のない手紙を書いています。 真心をこめて。 ルース・モートン・スコット バージニア州スコッツヴィル 19××年7月10日」 「ふふん」スコット・テイラーは笑いながら注釈をつけた。「いいだろう、この手紙を間違いなく無事に先方に届けてやろうじゃないか。ロバート・ゴードン閣下は2年前に死んじまったってことを、たまたま俺がしってるからというわけでな」 |