| Mr. Dick Gordon of New York, rich, indolent
and bored, tossed his morning paper
aside,
yawned, rose from the breakfast table
and
strolled wearily into the living room
of
his bachelor apartments. His man, who
was
busying himself about the room, looked
up
at his master questioningly. "I am wondering, Murphy," announced that young man, "what the devil we are going to do to assassinate time today." "Well, sir," replied Murphy, "you know you sort o' promised Mr. Jones as how you'd make up a four-flush at the Country Club this morning, sir." But the solemn-visaged Murphy shook his head in humble and horrified denial. "All right, Murphy; get my things out. I suppose I might as well do that as anything," resignedly. Languidly, Mr. Dick Gordon donned his golf togs and stood at last correctly clothed and with the faithful Murphy at his heels bearing his caddie bag. He crossed the living room toward the door of the apartment, halted half ways and turned upon his servant. "Golf's an awful bore, Murphy," he said. "Let's not play today." "Ha! I have it! Great morning for a ride. Hustle, you old snail, and fetch my things. Telephone Billy and tell him to bring Redcoat around. Get a move on!" By the time Murphy had attended to the various duties assigned him and returned from the telephone he found his young master sitting on the edge of a chair with one boot on and the other half so, staring hard at the floor, a weary expression on his face. "Can I help you, sir?" asked Murphy. "Yes, you can help me take off this boot. It's too hot to ride, and besides I don't want to ride anyway. What the devil did you suggest riding for, eh?" "Yes, sir." "I wish that you would say no, sir, for a change, Murphy. You're getting to be a terrific bore in your old age. Go and tell Billy to never mind Redcoat." "It won't be necessary, sir," said Murphy. "I didn't telephone for Redcoat in the first place, sir. I knew as how you would change your mind, sir, and thought it wouldn't be worth while calling up, sir." Gordon cocked his head on one side and surveyed his servant from head to foot for a long moment. "Yes, sir," he said, at last. Clothed again he wandered back into the living room, wishing that there was something in the world to hold his interest for a moment. The photograph of a handsome woman caught his eye. He picked it up and looked at it for several seconds. "I wish," he remarked, turning toward Murphy, "that there was something or some one on earth that could raise my temperature over half a degree." "Yes, sir," said Murphy. "That must be the mail man, sir," as an electric bell rang in the rear of the apartment and Murphy turned toward the door. A moment later he re-entered with a bundle of letters in his hand, laying them on Gordon's desk. The young man picked up the top envelope and opened it. One after another the young man opened the envelopes, nor did any succeed in erasing the bored expression from his countenance. The last he glanced at with a faint tinge of curiosity before opening. The feminine hand writing was unfamiliar, which was nothing unusual, but the postmark it was that drew his interest - Scottsville, Virginia. "Now, who the devil do I know in Scottsville, Virginia?" he asked himself as he drew his paper knife through the flap of the envelope. "Oh, it's addressed to Dad!" he exclaimed, suddenly noting his father's name upon the envelope. "Dear old Dad," sighed the young man; "I never lacked bully good company when you were alive, and I didn't know then what it meant to be bored. I wonder if you know how I miss you." He turned first to the signature at the close of the letter. "Ruth Morton Scott," he read. "H'm I've heard Dad speak of you, and Jefferson Scott, Jr., your husband, and the tragedy at the mission. Lord, what an awful place that must have been for a young girl! It was bad enough three years ago when Dad and I camped among its ruins; but twenty years ago the country must have been awful for white women." As Dick Gordon read the letter through slowly his face reflected for the first time in days a real interest. Toward the close he muttered something that sounded like "Damned cad," and then he carefully re-read the letter. After the second reading he sat upon the edge of his desk, the letter still in the hand that had dropped to his knee, and stared fixedly and unseeingly at the barbaric patterns of the Navajo rug at his feet. For ten minutes he sat thus; then he sprang up, animation reflected upon his face and determination in his every movement. Weariness and lassitude had been swept away as by magic. Seating himself at the desk he drew writing materials from a drawer and for ten minutes more was busily engaged in framing a letter. This done he rang for Murphy. "Skip out and post this, you old tortoise," he shouted, "and then go and book passage for the two of us on the first boat that sails direct or makes good connections for Mombasa - do you know where it is?" "Yes, sir; Africa, sir," replied the imperturbable Murphy, in as matter of fact a tone as though White Plains was to have been their destination. Mr. Dick Gordon always had been an impulsive young man, his saving characteristic being an innate fineness of character that directed his impulses into good channels, if not always wisely chosen ones. The following day, as Scott Taylor, mounted upon Generall Scott's favorite saddle horse, rode leisurely about "my plantation," as he now described the Scott estate, he chanced to meet the little wagon of the Rural Free Delivery carrier coming from town. "Anything for The Oaks?" he asked, reining in. The man handed him a packet of letters and papers, clucked to his bony old horse and drove on. Taylor ran through the letters. There was one that interested him - it bore the name and address of Richard Gordon on the flap. This he thrust into his inside pocket. Then he rode up the driveway, turned his horse over to a livery boy, and entered the library. It was empty, and laying the balance of the mail upon the table he made his way to his own room. Here he quickly opened and read Gordon's letter to Mrs. Scott. His eyes narrowed and his brows contracted with the reading of the last paragraph: "Father has been dead two years; but I know all about the location of the mission, as I visited it three years ago while lion hunting with him. As I am just about to leave for Africa again I shall make it a point to recover the papers you wish." Taylor crumpled the letter angrily in his hand. "The fool!" he muttered, "what does he want to butt in for?" Then came a knock upon the door and Taylor hastily crammed the letter into the pocket of his coat. "Come in!" he snapped, and an old Negress entered with fresh towels and bed linen. As she moved in her way about her duties Taylor sat with puckered brows and narrowed lids gazing through the window. It was not until the woman left the room that he arose. Now he seemed to have reached a decision that demanded rapid action. He snatched off his coat, throwing it across the bed, where it dropped over the side to the floor beyond. His trousers he flung on the floor; his shirt, collar and tie upon the center table, and in fifteen minutes he was dressed in fresh linen and another suit and cramming his belongings into his bag. Running downstairs and out to the stables, he shouted to a hostler to harness the team and take him to the station. Mrs. Scott and Virginia had the car out, so he was forced to content himself with the slower method of transportation. Forty-five minutes later he boarded a northbound train for New York, and late that night rang the bell of an apartment in West One Hundred and Forty-Fifth Street. A bleached blonde in a green kimono opened the door in response to his ring. "Why, hello, kid!" she cried when the dim light in the hallway revealed his features to her. "You're just in time for a snifter. Where you been keepin' yourself? Jim and me were talkin' about you not five minutes ago. Come on in; the gang's all here," and she grasped him by the lapel of his coat, drew him into the hall and slammed the door. "I've been doing the rural," replied Taylor with a laugh; "and, take it from me, it's mighty good to be back again where there are some live ones." He preceded the girl into the dining room of the little apartment. "Well, well! Little ol' kid back again!" cried one. "Hello, Jim! Hello, Bill!" cried Taylor, grasping their outstretched hands. "You sure look good to me." "Get another glass, Blanche," Jim called to the girl, "Sit in, kid, and we'll have a little round o' roodle - dollar limit - whatd'yu say?" "Piker game," sneered Taylor, with a grin, "I'm dealing in millions, just now. Throw your cards in the goboon and listen to me, if you want to make a hundred thou apiece." He paused to note the effect of his remark. "Quick, Blanche!" cried Jim. "Get the poor devil a drink. Can't you see he's dying of thirst and gone bug?" Taylor grinned. "I'm sure dying of thirst all right," he admitted, "but I'm not bug. Now listen - here's how, thanks! - you guys are broke. You always have been and always will be till you stop piking. Once in a while you pull down a couple of simoleons and then sweat blood for a week or so for fear you'll be pinched and get a couple of years on the Island. I've got a real proposition here; but it's a man's job, though there isn't any chance of a comeback because we'll pull it off where there's no lamp posts and no law." He paused and eyed his companions. "Spiel!" said Bill. Taylor narrated the events that had taken place during the past week. "And now," he concluded, "if this Buttinsky Gordon brings back that marriage certificate I can kiss all my chances goodbye, for there isn't a court in that neck of the woods that would give me a look in with that Scott chicken if she had a ghost of a case." "And you want us to?" Jim paused. "You guessed it the first time," said Taylor. "I want you to help me follow Gordon, take that paper away from him - croak him." For a moment the four sat in silence. "Why do you have to croak him?" asked the girl. "So he can't come back and swear that he seen the certificate," said Bill. "That would be just as good as the certificate itself in any court, against the kid." "There isn't the least chance of our getting in wrong either," explained Taylor, "because we can lay it all onto the natives or to an accident and there won't be anybody to disprove it - if we are suspected; but the chances are that we can pull it off without anyone being the wiser." "And what did you say we got out of it?" asked Bill. "A hundred thou apiece the day I get the property in my hands," replied Taylor. "If you could get hold of the certificate first it would be fine and dandy, but we're got to follow Gordon to Central Africa to find where it is, and by that time he'll have it. So the only chance we have is to pass him the K. O. and take it away from him. I'll sure breathe easier after I've seen that piece of paper go up in smoke." James Kelley and William Gootch were, colloquially, short sports. They had rolled many a souse and separated more than a single rube from his bank roll by such archaic means as wire tapping and fixed mills, but so far they never had risen to the heights of murder. "We'll?" said Taylor, after a long pause, during which the other two had drained their glasses while the girl sat revolving hers upon the table cloth between her fingers. "I'm game," announced Kelley, dodging the girl's eyes and looking sideways at Gootch. "So'm I'!" declared the latter. And so it happened that when Mr. Dick Gordon walked up the gangplank of the liner that was to bear him as far as Liverpool in his journey to Africa, three men, leaning over a rail on an upper deck, watched him with interested eyes. "That's him," said Taylor, "the tall one, just in front of the solemn looking party that resembles a Methodist minister crossed in love - only he ain't. He's Gordon's man." As neither Gordon nor Murphy were acquainted even by sight or repute with any of the precious three, the latter made no attempt to avoid them during the trip. It was Taylor's intention to scrape an acquaintance with Gordon after they had changed ships at Liverpool, when he would then know for certain Gordon's destination, and could casually announce that he and his companions were bound for that very point on a hunting expedition. All went well with his plans until after they had sailed from Liverpool for Mombasa, when the depravity which was inherent in Kelley and Gootch resulted in an unpleasantness which immediately terminated all friendly relations between Gordon and the three. Taylor had succeeded in drawing Gordon into conversation soon after sailing from Liverpool, when he casually remarked that he and his friends were bound for the country about Victoria Nyanza in search of lions. "Is that so?" exclaimed Gordon. "I am going into the neighborhood of Albert Edward Nyanza myself, and shall take the route from Mabido around the north end of Victoria Nyanza." And a common interest established, the two became better acquainted. 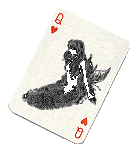 Then Taylor introduced his two friends and
later on Kelley suggested cards. Taylor tried
to find an opportunity to warn his accomplices
against the crookedness which he knew was
second nature with them. He would have preferred
to let Gordon win, but the estimable Messieurs
Kelley and Gootch, considering a bird in
the hand worth two in the jungle, swooped
down upon the opportunity thus afforded them
to fleece their prey. The result was that
after half an hour of opay Gordon rose from
the table, a rather unpleasant light in his
eyes, cashed in his remaining checks and
quit the game. Then Taylor introduced his two friends and
later on Kelley suggested cards. Taylor tried
to find an opportunity to warn his accomplices
against the crookedness which he knew was
second nature with them. He would have preferred
to let Gordon win, but the estimable Messieurs
Kelley and Gootch, considering a bird in
the hand worth two in the jungle, swooped
down upon the opportunity thus afforded them
to fleece their prey. The result was that
after half an hour of opay Gordon rose from
the table, a rather unpleasant light in his
eyes, cashed in his remaining checks and
quit the game."Why, what's the matter, old man?" queried Taylor, inwardly cursing Gootch and Kelley. "I wouldn't force an explanation if I were you," replied Gordon coldly. "The captain might overhear." "You boobs are wonders," sneered Taylor. "You must have made all of fifty dollars apiece out of it - and ruined every chance we had to travel right to the mission in Gordon's company," and he turned disgustedly away and sought his cabin. |
ニューヨークのディック・ゴードン氏は金持ちで、退屈で、そしてそれにうんざりしていた。彼は朝刊を脇に投げ出すと、あくびして朝食のテーブルから立ち上がり、独身者用アパートメントのリビングルームを疲れたようにぶらついた。その部屋で忙しそうにしていた彼の使用人は、いぶかしげに主人を見上げた。 「心配しているんだよ、マーフィー」と青年は言った。「時間をぶち殺すために今日我々はいったい何をしなけりゃならないのか、ってね」 「ご心配には及びません」マーフィーは答えた。「今朝はカントリークラブで、どのようにフォー・フラッシュの手を作るか、ジョーンズ様に約束のようなものをなさっていたではありませんか」  マーフィーはしかつめらしい顔で、慇懃さと計り知れぬ自制をこめて首を横にふった。
マーフィーはしかつめらしい顔で、慇懃さと計り知れぬ自制をこめて首を横にふった。「わかったよ、マーフィー、必要な物を出してくれ。たぶんなにをやったって同じようなものだ」諦めた口調だった。 ディック・ゴードン氏は気が乗らない様子でゴルフ着を着たが、結局はそれをすっかり身につけると、キャディバッグの重みを踵でこらえている忠実なマーフィーと並んで立った。アパートメントのドアに向かって半分ほどリビングルームを横切ったところで、彼は立ち止まって召使いを振り向いた。 「ゴルフなんてうんざりだ、マーフィー」と彼は言った。「今日はやめておこう」 「ハ! いいことがある! 乗馬には持ってこいの朝じゃないか。さあさあ老いぼれのカタツムリくん、急いで僕の持ち物を変えてくれ。ビリーに電話して乗馬服を持ってくるように言うんだ。早く早く!」 マーフィーがただちに言いつけられたさまざまな仕事をこなし、電話の所から戻ってきた時、若い主人は、ブーツが重ねて投げ出されている椅子の端に腰掛け、床をにらみつけていた。その顔には疲労が色濃く現れていた。 「どうなさいましたか?」とマーフィーは尋ねた。 「ああ、このブーツを片づけてくれ。乗馬には暑すぎる。それに僕はとにかく乗りたくないんだ。乗馬を勧めるなんて全く悪魔のしわざだぜ、え?」 「さようでございます」 「気分転換に『それは違います』とか言って見ろよ、マーフィー。そのご老体はおそるべき退屈そのものになりつつあるぞ。行ってビリーに乗馬服のことは忘れろと伝えてくれ」 「その必要はございません」マーフィーは言った。「私はそもそも乗馬服のことで電話をしておりません。私は、あなた様がどういうふうにお気持ちを変えるかを存じておりますので、その電話をかける価値はないだろうと拝察いたしました」 ゴードンは片側に首をかしげ、長い間、召使いの頭からつま先までを探るように見た。そして彼は言った「さようでございますか」 着替えると彼は、自分の興味を一瞬でも捉えるものがこの世界に無いものかと思い、リビングルームに戻ってぶらぶら歩き回った。端正な女性の一枚の写真が彼の目をとらえた。彼はそれを取り上げ、数秒の間それを見つめた。 「何でも、誰でも良いんだ」マーフィーに向き直って彼は言った。「僕の体温を半度でも上げてくれるものがこの地球上に無いものだろうか」 「さようでございますね」とマーフィーは言った。「郵便配達が来たようです」アパートメントの裏で電気ベルが鳴ったのでマーフィーはドアへ向かった。 彼はすぐに手紙の束を手に戻ると、ゴードンのデスクにそれを置いた。青年は一番上の封筒を取り上げて開封した。青年は次から次へと封筒を開けたが、どれひとつとして彼の表情から退屈の影を消すことに成功したものはなかった。最後のものを開封しようとして、彼はかすかな好奇心を持ってそれを見た。それは良く知らない女性の手書きのもので、特に変わった様子はなかったが、その消印が彼の興味を引いたのだ――ヴァージニア州スコッツヴィル、とそこにはあった。 「いったいヴァージニア州スコッツヴィルのどんな悪魔をこの僕が知っていると言うんだ?」彼は封筒の蓋にペーパーナイフを通しながら自問した。「おお、これは父さん宛だ!」封筒に書かれた宛名が父親の名前であることに突然気づいて、彼は叫んだ。「親愛なる父さん」青年はため息をついた。「父さんが生きていた時は、僕はいつもすてきな良き仲間に恵まれていた。そして退屈がどんなものなのかも知らなかった。父さんがいないのを僕がどれほど寂しく思っているか、あなたは知っていますか」 彼はまず手紙の末尾のサインを確かめた。「ルース・モートン・スコット」彼は読んだ。「フム、僕は父さんからあなたのことを聞いたことがある。そしてあなたの夫のジェファーソン・スコット・ジュニアのことや、布教所で起きた悲劇のことも。神様、それは若い娘にとってどんなにひどい場所だったことか! 僕と父さんがその廃墟でキャンプした3年前でさえ十分に悪い場所だったのに、20年も前、そこは白人女性にとって恐るべきところだったに違いない」 ゆっくりと手紙を読んでいくにつれ、ディック・ゴードンの顔にその日初めて何ものかへの本物の関心が現れた。終わり近くになって彼は「汚いやつめ」のように聞こえる何かをつぶやいた。そして、注意ぶかくもう一度手紙を読んだ。二度目に読み終わった後も彼は机の端に座っており、手紙は膝に落ちた手に依然として握られていた。そして足もとのナヴァホ族の敷物の荒削りな文様をじっと見るでもなく見つめていた。10分間もこうして座っていただろうか、彼は突然跳ね起きた。彼の顔には生気が漲り、行動にはことごとく決断があふれていた。疲れやけだるさは魔法のように消え去っていた。彼は机に向かって座り、抽斗から筆記用具を取り出すと、10分以上にわたって忙しく手紙をしたためた。それを終えると彼はマーフィーを呼んだ。 「急いでこれを投函してくれ、老いぼれ亀さん」彼は叫んだ。「それからその足で、モンバサに直行するかうまくそれに接続する最初の船に僕たち二人分の予約を入れるんだ。モンバサがどこにあるか知ってるか?」 「存じております、アフリカです」動ずることなくマーフィーは答えた。それは全くのところ、まるで目的地がホワイト・プレーンズででもあるかのような調子だった。 ディック・ゴードン氏はいつだって衝動的な若者なのだった。彼のもう一つの特徴はその生まれつきの純粋さであり、それは彼の衝動を良い方向へと導いていた――常に賢い選択であったとは言えないとしても。 その次の日のこと、スコット・テイラーはスコット将軍お気に入りの愛馬にまたがり、『わが荘園』(彼は今やスコット農園をそう称していた)をのんびりと乗り回していた。そして偶然、町からやってきた農園巡回便の小さな馬車に巡り会った。 「オーク屋敷になにかあるかね?」手綱を引きながら彼は尋ねた。 男は彼に手紙と新聞の束を手渡すと、年老いたやせ馬をけしかけて去っていった。テイラーは手紙に目を通した。1通の手紙が彼の目を引いた――その封筒の蓋にはリチャード・ゴードンの名前と住所が記されてあった。彼はそれを内ポケットへ押し込むとすぐに馬車道を駆け上がり、焦げ茶色の少年に馬を預けて書斎に入った。書斎は空っぽだった。彼はそのテーブルに残りの手紙を置くと、自室に向かった。部屋にはいると彼は素早くゴードンからスコット夫人に宛てた手紙を開け、そして読んだ。最後の部分に彼は目をそばめ、眉をしかめた。『父は2年前に亡くなりました。でも私はその布教所の場所を知っており、3年前に父とライオン狩りに行ったときにそこを訪れています。私はこれからすぐにまたアフリカへ発ち、あなたがお望みのその書類をかならず取り戻してきます』 テイラーは怒ってその手紙をわしづかみにした。「馬鹿野郎!」彼はつぶやいた。「何のつもりでこいつは首を突っ込んでくるんだ?」 その時ドアにノックの音がしたので、テイラーは急いで手紙を上着のポケットへ押し込んだ。 「入れ!」彼が指を鳴らすと、年取った黒人女が新しいタオルとシーツを持って入ってきた。彼女がその仕事を義務的に果たしている間、テイラーは眉をしかめ、目を細めて窓の外をじっと見つめていた。女が部屋を出ると彼は起きあがった。今や彼は素早い行動が必要だとの結論に達したようだった。彼は上着を引き剥がすとベッドに向こうに放り投げたので、それは反対側の床に落ちてしまった。彼はズボンを床に投げ捨て、シャツやカラーやタイはセンターテーブルに放り出した。そして15分の間に、彼は真新しいリンネルとスーツに身を包み、身の回りの品を鞄に詰め込んでいた。 彼は、階段を駆け下りてそのまま外へと走り出しつつ、馬車に馬をつないでただちに駅に連れていくように馬丁に叫んだ。しかしスコット夫人とヴァージニアが馬車で出掛けてしまっていたため、彼はより遅い運搬手段で満足せざるを得なかった。45分後、彼はニューヨークに向かう北行きの列車に乗り込んでいた。そしてその夜遅く、西145丁目のとあるアパートのベルを鳴らしたのだった。 彼のベルに応えて、緑のキモノを着た白茶けた金髪の女がドアを開けた。 「まあどうして? よくいらしたわね!」玄関の薄明かりで男の特徴を見定めるとその女は叫んだ。「ちょうどブランデーを飲(や)ってたところよ。一体どこに行ってたの? ほんの5分もしない前にジムとあたしであんたのことを話してたんだから。さあお入りなさいな。みんな揃ってるわよ」そして彼のコートの折り返しをつかむと室内に引っ張り込み、勢いよくドアを閉めた。 「俺は田舎でちょっとしたことをやってたのさ」テイラーは笑いながら答えた。「そして、よく聞けよ、俺はどえらい儲け話を持って、生きのいい奴らのところに戻ってきたんだ」 彼は女の先に立ってその小さなアパートのダイニングに入っていった。 「よっしゃ、よっしゃ! お仲間のお帰りだ!」一人が叫んだ。 「よう、ジム! よう、ビル!」彼らから伸ばされた手をつかんで、テイラーは叫んだ。「みんなに会えてうれしいぜ」 「もう一個グラスを持ってこい、ブランチ」ジムが女に叫んだ。「さあ座れよ、大将。ルードルのひと勝負でもしようじゃねえか――ただし掛け金は1ドルまでだがな。え、何だって?」 「けちなゲームだと言ったのさ」歯をむき出してテイラーはせせら笑った。「俺は今何百万という金を握っている。もしてめえらがしこたま分け前にあずかりたいと思ったら、そのタンツボへカードを投げ込んで俺のいうことを聞くんだな」彼は自分の提案の効果を見るために言葉を切った。 「早くしろブランチ!」ジムは叫んだ。「このかわいそうな野郎に飲ませてやれよ。カラカラで今にも死にかけて、虫の標本みてえになっちまってるのがわからねえのか?」 テイラーは歯をむきだして笑った。「いかにも俺は死にそうに喉が乾いている」彼は認めた。「でも虫になんかなっちゃいねえ。いいかよく聞け――ありがとよ――おめえたちは無一文だ。今までずっとそうだったし、そのけちなシノギをやめねえかぎりこれからもずっとそうだ。たまにせいぜい何ドルかの銭を稼ごうとしたら、1週間ばっかヒイヒイいって働くか、さもなきゃとっつかまってムショに何年かくらいこむのをビクビクして心配するかのどっちかだろう。いいか、この話は本物だ。男の仕事だ。しっぺ返しはあり得ねえ。なんてったって街灯も法律もねえところでやってのけようってんだからな」 彼は言葉を切って仲間を見た。 「つづけろよ!」ビルが言った。 テイラーは前の週の出来事を話した。 「それでだ、」彼は話を結んだ。「もしこのお節介野郎のゴードンがその結婚証明書を持って帰った日にゃ俺は幸運から一切合財おさらばってことになる。でもな、あの近辺にゃ裁判所なんて1個もねえし、スコットの娘っこも状況を良く分かってねえ、そこで俺にちょっとした思いつきが浮かんだってわけだ」 「で、それを俺たちにやれと?」ジムが遮った。 「初めて当てたじゃねえか」とテイラーは言った。「ゴードンを追いかけて書類を奪うのを手伝って貰いてえんだ。奴を始末するのをな」 ちょっとの間、4人は黙っていた。 「なんでそいつを始末しなくちゃならないの?」女が聞いた。 「そりゃあ、奴が戻って来てその証明書を見たことを証言できねえようにするためさ。」ビルが言った。「その証言は、どんな裁判所でだって証明書そのものと同じくらい効くだろうぜ。この大将に対してな」 「俺たちがしくじるなんてことは万に一つもあるはずがねえ」テイラーは説明した。「なぜって俺たちはそれを全部原住民どもの中か、さもなければ偶然を装ってやるんだから、それを見とがめる奴なんているわけがねえじゃねえか。万が一疑われたとしても、俺たちより賢い奴はいねえんだから、いくらでも切り抜けるチャンスはあるさ」 「それで、俺たちがそれをやらかしたあとはどうなるんだって?」とビルは聞いた。 「財産が俺のものになったその日に10万ずつだ」テイラーは答えた。「もしお前がその証明書を真っ先に手に入れることが出来たら、そりゃカッコよくて気分もいいだろうぜ。だがな、俺たちは、中央アフリカでゴードンがその場所を見つけて書類を手にするまで、奴の後について行くんだ。そして、一度きりのチャンスに、俺たちは奴をノックアウトしてそいつを奪うんだ。その紙っきれの煙が空に上ってった後に、俺はやっと安心して息が出来るようになるだろうよ」 ジェイムズ・ケリーとウィリアム・グーチは、いわゆるケチなチンピラだった。彼らはワイヤで叩いたり拳骨で殴ったりという古典的なやり方で、何度も酔っぱらいの身ぐるみを剥ぎ、また田舎者から札束を巻き上げることも一度ならずあったが、今だかつて人殺しに手を染めたことまではなかったのだ。 「どうだ、やるのか?」長い沈黙の後テイラーが言った。その間、二人の男はグラスを空にし、女はテーブルクロスの上で自分のグラスを指で回し続けていた。 「俺は乗るぜ」女の視線を避けつつ、グーチを横目で見やりながらケリーが宣言した。 「俺もだ」ともう一人も言った。 アフリカ旅行に向かうディック・ゴードン氏がリヴァプール行き定期船の道板を上っていったとき、三人の男たちが上甲板の手すりから身を乗り出して興味深げに彼を見つめていたのには、そういういきさつがあったのだった。 「あれだ」テイラーは言った。「あの背の高い奴だ。丁度まるでメソジスト派の牧師が失恋したみてえな辛気くさい団体の手前にいる。――あいつは違う、あれはゴードンの召使だ」 ゴードンもマーフィーも、この物騒な三人について、見かけにしろ評判にしろ何の知識も無かったので、旅行中彼らを近づけないような手をマーフィーは一切講じていなかった。ゴードンとなんとか面識を得ることが、リヴァプールで船を乗り換えて以来のテイラーの目的だった。彼はゴードンの目的地を既に心得ていたから、彼とその仲間とが狩猟の旅のためにまさにその地点に向かっているということを偶然を装って伝えるのは造作もないことだった。 モンバサに向けてリヴァプールを出帆してしばらくは、彼の計画はすべてうまくいっていた――ケリーとグーチの生まれつきの腐った根性が、ゴードンと三人の間の良好な関係の一切を不愉快な形であっという間に終わらせてしまうまでは。テイラーはリヴァプールを出帆してすぐにゴードンを会話に引き込むことに成功していた。その時彼は、自分は友人たちと一緒にライオンを求めてビクトリア・ニャンザの一帯へ向かっているのだと何気なく言ったのだ。 「本当に?」ゴードンは叫んだ。「ぼくの方もアルバート・エドワード・ニャンザの一帯に入ろうとしてましてね、たぶんマビドからビクトリア・ニャンザの北の端を回ることになるでしょう」共通の関心事を見つけたことにより、二人はより親しくなった。 そしてテイラーは二人の友人を紹介したが、そのあとケリーがカードをやろうと言い出した。テイラーは、共犯者たちの第二の天性であるいかさま狙いをしないよう、彼らになんとか警告しようとした。彼はゴードンに勝たせたかったのだが、尊敬すべきケリーとグーチのご両所は『手の中の一羽の鳥はジャングルの中の二羽に相当する(明日の百より今日の五十)』と考えて、獲物から巻き上げることの出来る機会を逃しはしなかった。テーブルからゴードンが立ち上がったのは始めて半時間ほどのことだった。彼は目を不愉快そうに光らせ、残りのチップを全部現金に替えるとゲームをやめてしまった。 「なぜです?どうしたのですか?」心の中でグーチとケリーを呪いながらテイラーは尋ねた。 「もしぼくがあなただったら、説明を求めたりしませんよ」冷ややかにゴードンは答えた。「船長の耳にも入るでしょう」 「てめえらのまぬけさ加減にはあきれたよ」テイラーはあざ笑った。「てめえらは全部ひっくるめて一人あたま50ドルがとこ稼いだには違えねえ。だがな、そのおかげで、大目的のために俺たちがゴードンと一緒に旅行できるかも知れなかったチャンスが全部台無しになっちまったんだ。」そして、うんざりしたように顔をそむけると船室に戻っていった。 |