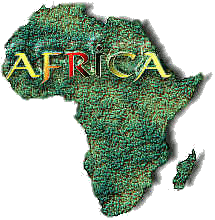
CHAPTER III /第3章
e-txt:小林信也
翻訳:おかぴー
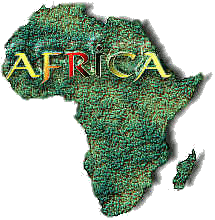
| Sophronia was blithely humming as she went
about her work on the second floor
of the
Scott house. Occasionally she broke
the monotony
by engaging in heated discussions with
herself. "Yes," she said, shaking her head. "I never did like that Mister Scott Taylor. He may be poor Miss Dorothy's boy; but he's trash, just the same. Yes. And look here," as she pushed the bed out from the wall to ply her broom beneath. "Just look here! There he's gone and left his coat. Shiftless, that's what he is - throwing his coat around like that," and she seized the garment with a vigorous shake. Throwing the coat across her arm, the maid carried it down to the library, where Mrs. Scott and Virginia were sitting. "Here's that Mister Scott Taylor's coat," she announced, laying it on the table. "What am I going to do with it - give it to Samuel?" "No, Sophronia," said Mrs. Scott, "we'll have to send it to him," and she picked up the garment to wrap it for mailing. As she folded it a crumpled sheet of note paper fell from a side pocket. Virginia picked it up to replace it in the coat, when, by chance, she saw her mother's name upon the top of the sheet. "Why," she exclaimed, "this is yours, mother," and she spread the note out, smoothing it upon the table top. "It's a letter to you. How in the world did it happen to be in Scott's coat?" Mrs. Scott took the note and read it; then she handed it to her daughter. When Virginia had completed it she looked up at her mother, her face clouded and angry. "Why, the scoundrel!" she exclaimed. "He actually has been intercepting your mail." Then she glanced again at the date line and her eyes opened wide. "Mother!" she cried. "This letter must have come the very day Scott left in such a hurry. It must have been because of this letter that he did leave. What can it mean?" Mrs. Scott shook her head. "I know," announced Virginia. "He has gone to prevent Mr. Gordon from recovering the certificate or else to follow him and obtain possession of it himself. There could be no other explanation of his hurried departure, immediately after the receipt of this letter." "It does look that way, Virginia; but what can we do?" "I can go to New York and talk with Mr. Gordon," said Virginia, "and that is just what I shall do." "But, my dear - " Mrs. Scott started to expostulate. "But I am," said Virginia determinedly, and she did. To her dismay she found Mr. Richard Gordon's apartment locked and apparently untenanted, for there was no response to her repeated ring of the bell. Then she inquired at another apartment across the hall. Here a house man informed her that Mr. Gordon's man had told him that he and Mr. Gordon were leaving for Africa - he even recalled the name of the liner upon which they had sailed for Liverpool. What was she to do? Well, the first thing was to assure herself as to whether Scott Taylor had also sailed for Africa, and if not to arrange to have him watched until she could get word to Mr. Richard Gordon. The taxi that had brought her to Gordon's apartment was waiting at the curb. Descending to it, she gave the driver instructions to take her to the office of a certain steamship company - she would examine the passenger list and thus discover whether Taylor had sailed on the same boat with Gordon; but after examining the list and finding Taylor's name not among those of the passengers it suddenly occurred to her that the man would doubtless have assumed a name if his intentions were ulterior. Now she was in as bad a plight as formerly. She racked her brain for a solution to her problem. It would do no good to wire Gordon, for he would not know Taylor if he saw him, and anyway it was possible that Taylor had not followed him and that she would only be making herself appear silly by sending Gordon a melodramatic wireless. "I only wish," she muttered to herself, "that I knew whether or not Scott Taylor has followed him to Africa. How can I find out?" And then came a natural solution of her problem - to search for Scott Taylor himself in New York. Her first thought was of a city directory, and here she found a Scott Taylor with an address on West 145th Street, and a moment later her taxi was whirling her uptown in that direction. It was with considerable trepidation that Virginia Scott mounted the steps and rang the bell beneath the speaking tube. She feared Taylor and knew that she was doing a risky thing in thus placing herself even temporarily in his power; but loyalty and gratitude toward Richard Gordon, a stranger who had put his life, maybe, in jeopardy to serve her and her mother, insisted that she accept the risk, and so when the latch of the front door clicked and a voice, ignoring the speaking tube, called down from above for her to come up, she bravely entered the dark stairway and marched upward, to what she had no idea. She had been glad to note that the voice from above had been that of a woman. It made her feel more at her ease; but when she reached the topmost step and found a slovenly young woman with bleached hair and a green kimono awaiting her, her heart sank. "Does Mr. Scott Taylor live here?" she asked. "Yes, but he ain't at home. What do you want - anything I can do for you?" "Has he left the city?" asked Virginia. The girl's eyes narrowed, and Virginia noted it, but she thought, too, that she saw a trace of fear in them. She was convinced that this woman could tell her all she wished to know, but how was she to get the information from her? "May I come in a moment and rest?" she asked. "It's rather a long climb up here from the street," and she smiled - one of those delightful smiles that even a woman admires in another woman. "Sure!" said the girl. "Come right in. Don't mind how things look. I'm here alone now and takin' it easy. You have to keep things straightened around here when the men folks are home, or they're always growlin'." "What a cute little place you have here," said Virginia. "You are Mrs. Taylor?" The girl flushed just a trifle. "No," she replied. "My man's name is Kelley. Mr. Taylor boards with us when he's in town." And afterward when she addressed her as Mrs. Kelley, Virginia could not but note an odd expression around the corners of the girl's mouth. "Is Mr. Taylor out of town now?" asked Virginia. "Say, look here," she demanded at last. "What's your game? Who are you, anyhow and what's your idea in doin' all this rubberin' after Kid Taylor?" For a moment Virginia did not know what answer to make, and then, impulsively, she decided to tell this girl a part of her conjectures at least, in the hope that either sympathy for Gordon or fear of the consequences upon Taylor would enlist her services in Virginia's behalf. There was that in the girl's face which convinced Virginia that beneath the soiled green kimono and evidences of dissipation in the old-young face there lay a kind heart and a generous disposition. And so she told her. "I don't know," she said, "what strings Kid Taylor has on me. He ain't never done nothing except to egg Jim on first to one job and then to another that Taylor didn't have the nerve to pull off himself. Jim's been to the Island once already for a job that Taylor worked up an' then sat right here drinkin' high-balls an' tryin' to flozzie up to me while Jim and Bill were out gettin' pinched. "An' now - " she paused, a startled look coming into her eyes. "An' now he's framed up a murder for them, 'cause he ain't got the nerve to do it himself." "You mean," cried Virginia, "that they have really followed Mr. Gordon to Africa to murder him?" Blanche nodded, affirmatively. Then she leaned forward towered her caller. "I've told you," she said, "because I thought you might find a way to stop them before they did it. I don't want Jim sent to the chair. He's always been good to me. But for Gawd's sake don't let them know I told you. Bill 'ud kill me, an' Jim 'ud quit me, I'd care more about that than the other. You won't tell, will you?" "No," said Virginia, "I won't. Now, tell me, they sailed on the same boat as Mr. Gordon?" "Yes, Jim and Bill and Taylor, an' they were goin' to follow Gordon until he got the paper, then croak him an' take it away an' say it was an accident or something." Virginia Scott rose from the chair upon which she had been sitting. For a moment Virginia stood in silence. Then she held out her hand to the young woman. "I thank you," she said. "You have done right to tell me all that you have. Goodbye!" "What are you going to do?" asked Blanche. "I don't know yet," replied Virginia. "I want to think - maybe a solution will come." And as she was driving back to her hotel the solution did come - in the crystallization of a determination to take the saving of Richard Gordon into her own hands. It was for her that he was risking his life. She would be a coward to do one whit less than her plain duty. There was no one upon whom she could call to do this thing for her, since she realized that whoever attempted it must risk his life in pitting himself against Taylor and his confederates - desperate men who already had planned upon one murder in the furtherance of their dishonorable purpose. She thought of writing her mother first; but deliberation assured her that her parent would do everything in her power to prevent the carrying out of a scheme which Virginia herself knew to be little short of madness - and yet she could think of no other way. No, she would wait until it was too late to recall her before she let her mother know her purpose. So instead of returning at once to her hotel, Virginia drove to the offices of a transatlantic steamship company, where she made inquiries as to sailings and connections for Mombasa, Africa. To her delight she discovered that by sailing the following morning, she could make direct connections at Liverpool. Once committed to her plan she permitted no doubts to weaken her determination, but booked her passage immediately and returned uptown to make purchases and obtain currency and a letter of credit through a banker friend of her grandfather. The morning that she sailed she posted a long letter to her mother in which she explained her plans fully, and frankly stated that she had intentionally left her mother in ignorance of them until now for fear she would find the means to prevent their consumation. "I know that, to say the least," she wrote, "the thing that I am going to do is most unconventional and I realize also that it is not unfraught with dangers; but I cannot see a total stranger sacrifice his life in our service without a willingness to make an equal sacrifice, if necessary, in his." And when her mother read the letter, though her heart was heavy with fear and sorrow, she felt that her daughter had done no more than the honor of the Scotts demanded. To Virginia the long journey seemed an eternity, but at last it came to an end and she found herself negotiating with an agent at Mabiso for native porters and guards and the considerable outfit necessary to African travel. From this man she learned that Gordon had left for the interior a month before, but he had not heard of a man by the name of Taylor, though there had been, he said, another party of three Americans who had followed Gordon by about a week. These had been bound for Victoria Nyanza to hunt, and the agent smiled as he recalled their evident unfamiliarity with all things pertaining to their avocation. Virginia asked him to describe these men, and in the description of one she recognized Taylor, and rightly guessed that the others were Kelley and Gootch. So three men, one of them an unprincipled scoundrel, had gone out into the savage, lawless wilds on the trail of Richard Gordon! Virginia went cold as the fear swept her that she was too late. This hope sustained her; that Gordon with his superior knowledge and experience had been able to outdistance the others, and that she, by traveling light and carefully selecting her path, might overtake them before they overtook Gordon or met him upon his return. With this idea in mind Virginia hastened her preparations, and once on the march urged her safari on to utmost speed. Almost from the start she discovered that her head man, while apparently loyal to her, had but meagre control of the men of the safari, who were inclined to be insubordinate and quarrelsome. The result was that to her other burdens was added constant apprehension from this source, since it not only threatened her own welfare but the success of her mission as well. It was upon the tenth day that the first really flagrant breach of discipline occurred - one which the headman could not handle or the girl permit to pass unnoticed. The men had long been grumbling at the forced marching which had fallen to their lot since the very beginning, notwithstanding the fact that they had been employed with the distinct understanding that such was to be the nature of their duty. Today, after the mid-day rest, the porters were unusually slow in shouldering their packs, and there was much muttering and grumbling as the headman went among them trying to enforce his commands by means of all manner of terrible threats. Some of the men had risen sullenly and adjusted their burdens, others still sat upon the ground eyeing the headman, but making no move to obey him. Virginia was at a little distance waiting for the safari to set out. She was a witness to all which transpired. She saw a hulking black Hercules slowly raise his pack in laggard response to the commands of the excited headman. Just what words passed between them she could not know, but suddenly the porter hurled his load to the ground, shouting to the others who had already assumed their burdens. One by one these followed his example, at the same time shouting taunts and insults at the frantic, dancing, futile headman. The armed members of the party - the native escort - leaned on their rifles and grinned at the discomfiture of the headman. Virginia's heart sank as she witnessed this open break. It was mutiny, pure and simple, and her headman was quite evidently wholly incapable of coping with it. That it would quickly spread to the armed guard she was sure, for their attitude proclaimed that their sympathies were with the porters. Something must be done, and done at once, nor was there another than herself to do it. Virginia came to a decision quickly. She crossed the space between herself and the porters at a rapid walk, shouldering her way between the watchers until she stood between the headman and the bellicose porter. At sight of her they stopped their wrangling for a moment. Virginia turned to the headman. "Tell this man," she said, "that I say he must pick up his pack at once." The headman interpreted her order to the mutineer. The latter only laughed derisively, making no move to obey. Very deliberately Virginia drew her revolver from its holster at her hip. She levelled it at the pit of the porter's stomach, and with a finger of her left hand pointed at the pack on the ground. She said nothing. She knew that she had committed herself to a policy which might necessitate the fulfillment of the threat which the leveled weapon implied, and she was ready to adhere to the policy to the bitter end. The fate of her expedition hung upon the outcome of this clash between her porters and her representative, the headman; and upon the fate of the expedition hung, possibly, the very life of a stranger who had placed himself in jeopardy to serve her. There was no alternative - she must, she would compel subordination. The porter made no move to assume his burden, but he ceased to laugh. Instead, his little eyes narrowed, his heavy lower jaw and pendulous lower lip dropped sullenly. He reminded the girl suddenly of a huge brute about to spring upon its prey, and she tightened the pressure of her finger upon the trigger of her revolver. "Tell him," she instructed the headman, "that punishment for mutiny is death. That if he does not pick up his pack at once I shall shoot him, just as I would shoot a hyena that menaced my safety." The headman did as he was bid. The porter looked at the encircling faces of his friends for encouragement. He thought that he found it there and then an evil spirit whispered to him that the white woman would not dare shoot and he took a step toward her threateningly. It was his last step, for the instant that he took it Virginia fired, not at his stomach, but at his heart - and he crumpled forward to tumble at her feet. Without a second glance at him she wheeled upon the other porters. "Pick up your packs and march!" she commanded, and those who could not understand her words at least did not misinterpret the menace of her levelled weapon. One by one, and with greater alacrity than they had evinced since the first day out, they shouldered their burdens, and a moment later were filing along the trail. The safari still grinned, for which Virginia was devoutly thankful. From then on she became her own headman, using that dignitary principally as an interpreter. |
ソフロニィアは、スコット家の2階で、仕事をする時、楽しそうに鼻歌を歌っていた。時折、彼女は自分相手の激しい討論に引き込まれることにより、単調な気分を変えていた。 「ええ」彼女は頭をふりながら、言った。「私は、ミスタースコット・テイラーを好きになんか決してなれないですよ。あの人はたしかに可哀想なミス・ドロシーの息子に違いないかしれないけど、彼は、くずですよ。まさに、それと同じ。ええ、見てごらんなさいまし。」彼女は下のほうをほうきではきだすために、壁からベットを押して動かした。「ほら、みてごらんなさい! コートをおきっぱなしにして、行っちゃってますよ。だらしがない、それが、彼なんですよ。コートをこんなふうにあちこち投げ捨てちゃって……」彼女はその衣服をいきおいよく揺さぶりながら、つかんだ。 それを、自分の腕の中に投げ込むと、メイドは、下の書斎に持っていったが、そこにはスコット夫人とヴァージニアが座っていた。 「ミスター・スコット・テイラーのコートですよ」彼女はテーブルにそれを置きながら知らせた。「それを私はどうしたらいいでしょうか? サムエルにくれてやりましょうか?」 「だめですよ。ソフロニィア」スコット夫人が言った。「私たちは、それを彼に送り届けてあげないといけませんよ」そして、彼女は郵便でおくるために、その衣服を包もうと取りあげた。彼女がそれを折りたたもうとしたとき、くちゃくちゃにされたメモの紙がわきのポケットから落ちた。ヴァージニアは、それをつまみあげ、コートの中にもどそうとしたが、その時、偶然にも、彼女は紙のてっぺんに母親の名前があるのを見つけた。 「あら」彼女は叫んだ。「これは、お母様のものですわ」そして、彼女はそのメモをテーブルの上にのばしながら、ひろげた。「これは、あなた宛の手紙だわ。いったい全体どうして、スコットのポケットにこれが入っているのかしら?」 スコット夫人はそれをとりあげて、読んだ。それから、彼女は娘に手渡した。ヴァージニアは、読み終えると、顔を怒りで曇らせて、母親を見た。 「ああ、なんてひどい奴!」彼女は叫んだ。「彼ときたら、なんとあなた宛ての手紙を横取りしたのね」それから、彼女は再び消印のところを見て、瞳を大きく開いた。「お母様!」彼女は悲鳴をあげた。「彼がこんなにあわてて出発したのは、まさに、この手紙がきた日に違いないわ。この手紙のせいで、彼は出発しなくてはならなかったのよ。それは何を意味するのかしら?」 スコット夫人は頭を振った。 「私にはわかるわ」ヴァージニアは言った。「彼はゴードンさんが、証明書をとりもどすのを邪魔するつもりか、さもなければ、ゴードンさんについていって、それを彼自身のものにしようと思っているのよ。この手紙をうけとったすぐあとの、彼のあわだたしい出発の説明にはそれ以外のことはありえないわ」 「どうやらそのようね。ヴァージニア。でも、私たちに何ができるのかしら?」 「私がニューヨークに行ってゴードンさんに話すことができるわ」ヴァージニアは言った。「それが、まさに、私のやるべきことなのではないかしら」 「でもね、ヴァージニア」スコット夫人はいさめようとした。 「私はやるわ」ヴァージニアははっきりと言うと、そうした。 しかし、彼女が狼狽したことには、リチャード・ゴードン氏のアパートの部屋は鍵をかけられ、だれもいないことがあきらかであった。それは、彼女が繰りかえしてならした呼び鈴に対していかなる反応もなかったからだった。それで、彼女は廊下の反対側のほかの部屋の居住者に尋ねた。 その家の男は、ゴードン氏は、アフリカに旅立つと彼に話しをしたと知らせてくれた。彼は、その定期船の名前まで思い出してくれたが、船はすでに、リバプールにむかって出航したあとだった。 彼女ができることは何か? さて、たしかな最初のことは、スコット・テイラーも、アフリカに出航したかどうかであり、もし違うなら、彼女がリチャード・ゴードン氏に知らせるまで、彼を見張る手はずを整えないといけないことであった。ゴードンのアパートに彼女をつれてきたタクシーが、歩道と車道の間のへりで待っていた。そこへ降りていくと、彼女は、とある汽船会社のオフィスにつれていくようにと運転手に命じた。そこで、彼女は乗客名簿を調べることで、テイラーが、ゴードンと同じ船で、出港したかどうか、知るつもりだった。彼女がリストを調べ、テイラーの名前を乗客たちの中で発見できなかったあと、もし彼の目的が隠されたものなら、あの男は疑いなく偽名を使うに違いないということが、突然彼女の心に浮んだ。いまや、彼女は以前と同じひどい、苦境に陥ってしまった。彼女は自分の問題の解決のために脳みそをしぼった。ゴードンに電報をうつというのも、よいやり方ではなさそうだし、なぜなら、もし彼がテイラーに会ったとしても、彼だとは見分けがつくはずはないだろうし、とにかく、テイラーがもし彼についていかなかったのなら、ゴードンに芝居がかった電報を送ってしまい、彼女を愚か者に見せるだけという可能性もあった。 「私が望むことはただ」彼女は自分自身につぶやいた。「スコット・テイラーが、彼についてアフリカへ行ったかどうかを知ることだけなの。どうやったら、それを知ることができるのかしら?」 それから、彼女の問題にたいする妥当な解決法をとることとなった。それは、ニューヨークで、スコット・テイラーを捜すということである。彼女の最初の考えは街の住所氏名録であり、そこで、彼女は西145番街の住所のスコット・テイラーを見つけた。そして、一瞬ののちには、タクシーが、彼女をその方向にある住宅街へと運んでいった。ヴァージニアは戸口の階段をのぼり、通話管の下にあるベルをならすとき、ひどくおびえていた。彼女はテイラーを恐れていた、そして、自分がこのように一時的でさえ彼の勢力内にわが身をおくという、危険なことをしているのを理解していた。しかし、リチャード・ゴードン、自分の命をかけてくれた見知らぬ人、そしてたぶん、彼女と彼女の母親のために、働くことで危険な目にあうであろう彼に対する忠実と感謝の念が、彼女にそのリスク受け入れるようにと、強く主張した。さて、玄関の掛け金がカチリと音をたてると、通話管を無視して、上のほうから、あがってくるようにと、彼女をよびかける声がした。彼女は勇敢にも暗い階段の中に入り、上へ進んだ、それしか彼女にはなんの考えもなかった。彼女は上のほうから聞こえてきた声は女性のものに違いないと気づき喜んでいた。彼女の気分はぐっと楽になったが、階段のてっぺんに着いて、漂白した髪で、緑の着物をきただらしのない若い女性が彼女を待っていたのを見つけたとき、心が沈んでしまった。 「スコット・テイラーさんは、こちらにお住まいですか?」彼女は尋ねた。 「ええ、でも彼は家にはいないわよ。何が欲しいの?あたしがあんたに、できることなんかある?」 「彼は街を離れたのかしら?」ヴァージニアはたずねた。 その娘の目は狭められ、ヴァージニアは、それに気づいた、しかし、彼女はその瞳の中にわずかな怖れを見たとも思った。彼女はこの女性が、彼女の知りたいことすべてを話すことができると確信したが、どうやって、彼女から情報をひきだしたらいいのか? 「しばらく中に入って、休んでもいいかしら?」彼女はきいた。「通りからここまでかなりの登り道だったでしょう」そして、彼女は微笑んだ。女性ですらほれぼれするような楽しそうな笑いのひとつが、もうひとりの女性にもひろがった 「もちろんよ」その娘は言った。「こちらへ、いらっしゃいよ。どんなふうに見えるかなんて気にしなくていいわよ。今、あたしひとりきりなんだから、くつろいでちょうだい。男どもが家にいるときには、あんたもちゃんとしてないといけないでしょうけどね、さもないと、あいつら、がみがみ言うものね」 「ここで、あなたはなんてかわいらしい小さなお部屋を持っているのかしら」ヴァージニアは言った。「あなたは、ミセス・テイラーなの?」 その娘は、ほんの少し顔を赤らめた。「違うよ」彼女は答えた。「あたしの男の名前はケリーだよ。テイラーさんは、街にいるときには、うちに下宿しているのさ」 その後は、ヴァージニアは、彼女をミセス・ケリーとして、話したが、娘の口のすみのあたりにうかんだ奇妙な表情にはまったく気づかなかった。 「テイラーさんは、今、街からでたのかしら?」ヴァージニアは質問した。 「あのね、話してちょうだい」最後には、彼女は強く尋ねた。「あんたの魂胆はなんだい? あんたが誰だろうと、とにかく、あのテイラーのガキの行く先を、すべて聞きたがるのは、どういうつもりなんだい?」 一瞬、ヴァージニアはどう答えたらいいかわからなかったが、それから、衝動的に、この娘に、少なくとも、彼女の推測の一部を話す決心をした。それは、娘がゴードンに対する同情か、もしくは、テイラーに対する恐怖のせいで、ヴァ−ジニアのために協力してくれることを願ってのことだった。しみのついた緑の着物のしたの、若いのに老けて見える娘の顔は放蕩のあとが残ってはいたが、やさしい心と思いやりの気持ちがあることを、ヴァージニアに確信させた。それで、彼女は娘に話した。 「あたしは知らないよ」彼女は言った。「テイラーのガキが、あたしをどうあやつるつもりだったかなんてね。あいつは、最初から、自分ではあつかましくてやってのけれないような仕事を次から次へと、ジムにおだててさせること以外はなにもしなかったのさ。ジムは、もうすでに一度テイラーにあおられた仕事で、島にいたことがあるんだよ、で、あおったテイラーはまさにここで、ハイボールを飲んで、ジムとビルが、逮捕されていない間、あたしに売春をさせようとしたのさ」 「そんで、今度は」彼女はいったん口篭もり、驚いたような表情が彼女の目にうかんだ。「そんで今度は、あいつらを人殺しに仕立てようってのかい。あいつが自分ではそれをできそうにもないって理由でね」 「あなたのおっしゃる意味は」ヴァージニアは叫んだ。「彼らはゴードンさんを殺すためにアフリカまで実際、彼のあとについて行ったということかしら」 ブランチは、肯定するように、うなづいた。そして、彼女の訪問者の前方に立ち上がり、身をのりだした。 「あたしが、あんたに話したのは、」彼女は言った。「あんたなら、あいつらがそれをする前に、とめてくれる方法をみつけてくれるに違いないと考えたからなんだよ。あたしは、ジムを電気椅子なんかに送りたくないんだよ。彼はいつも、あたしには親切にしてくれているのさ。でも、グーチのために、あたしがあんたに話したということを、彼らに知られないようにしてよ。ビル(グーチのこと。)は、あしたを殺すに違いないし、そしてジムはあたしと別れるに違いないからね。あたしは、そのことが、ほかのこと以上に気にかかるんだよ。あんたは、話さないだろうね」 「ええ」ヴァージニアは言った。「私は話さないわ。さあ、言ってちょうだい。彼らはゴードンさんと同じ船で出航したのかしら」 「そうだよ。ジムとビルとテイラーで、ゴードンが書類を手に入れるまで、彼のあとをついていくつもりなんだ。それから、彼を殺して、それを奪い、事故か何かがあったというんだ」 ヴァージニア・スコットは、座っていたイスから立ち上がった。 しばらくの間、ヴァージニアは無言で、立ちあがったままだった。それから彼女は、その若い女性に彼女の手を差し出した。 「ありがとう。」彼女は言った。「あなたは知っていることのすべてを私に話すという正しい行いをしたんだわ。さようなら!」 「あんたはどうするつもりなんだい?」ブランチはたずねた。 「私にもまだわからない。」ヴァージニアは答えた。「私は考えたいの。そしたら、たぶん、答えを思いつくわ。」 そして、彼女は自分のホテルに車でもどる途中に、答えを見いだした。それは、リチャード・ゴードンを彼女自身の手ですくうという決心が具体的になったものだった。彼女のために、彼は、命を危険にさらしていた。自分のあきらかなる義務を少しもはたさなければ、彼女は卑怯者となるだろう。テイラーと彼の共謀者と戦おうするものは、だれでも、命を危険にさらすに違いないと彼女は理解していたので、これを行なう自分のために、だれかを呼ぶことができなかった。というのも、死に物狂いの男たちは、彼らの卑劣な目的を進めるために、すでにひとつの殺しを計画していたからだった。 彼女は最初、自分の母親に手紙を書こうと考えたが、熟慮のすえ自分でもちょっと正気のさたではないという計画を実行するのを妨げるためには、彼女の母親は、その力でなんでもやるであろうと確信した。それに、ほかのやり方をまだ彼女は考え付くができなかった。いや、母親に自分の目的を知らせる前に呼び戻されたら手遅れになってしまうと思うと、彼女はもう待てなかった。 それで、ヴァージニアはすぐに自分のホテルにもどるかわりに、大西洋横断汽船会社のオフィスに車を走らせ、そこで、アフリカのモンバサに向かう船と接続便を問い合わせた。嬉しいことには、彼女は次の朝出航する船を見つけることができ、リバプールにいる接続便に直行することができた。ひとたび、自分の計画に没頭すると、彼女は自らの決心をひるがえそうというなんの疑いも許さなかった、彼女の航海はただちに予約され、そのほか、買物と祖父の友人の銀行員をとおして、通貨と信用状を手に入れるために、彼女はアップタウンにもどった。 出航する朝、彼女は、母親に長い手紙をだし、そこで、十分に自分の計画を説明し、自分が見つけ出した彼らが成就することをさまたげる方法に母親が心配しないように、今まで彼らのことを知らないままにさせていたと率直に述べた。 「私は少なくともなんておっしゃるかわかっています。」彼女は書いた。「私がしようとしていることは、まったく慣例にしたがわないことですし、危険をはらんでいないことだとも、思っていません。でも、私は同等の犠牲を、喜んで払うことなしに、まったくの見知らぬ方が私たちにつくしてくださるために、命を犠牲にするのを見てはいられないのです。もし、必要なら彼の命と同等の犠牲をです」 彼女の母がその手紙を読んで時、その心は、不安と悲しみで重くなったが、自分の娘はスコット家の名誉が要求したことをしたにすぎないと母は感じた。 ヴァージニアにとって、長い旅は永久に続くかのように思われたが、ついに、その終わりがきた。そして、彼女は、アフリカの旅に必要な現地人のポーターとガイドと、かなりのしたく品一式のことで、マビソの仲介屋と、交渉している自分自身に気づいた。この男から、彼女は、ゴードンがひと月前に、すでに奥地に出発したことを知った。しかし、仲介屋が言うには、およそ1週間のうちに、ゴードンの後をついていった3人のほかのアメリカ人の一行もいたが、そこでも、テイラーという名前の男のことは聞いたことがなかったということだった。 これらの者たちは、狩りをするために、ビクトリア・ナンザに向かうということだったが、、仲介屋は、彼らが自分たちの趣味に関係するすべてのことにあきらかに不案内だったことを思い出して笑った。 ヴァージニアはこれらの男たちの様子を話してくれと、彼に頼んだ。そして、その描写で、ひとりがテイラーであるとわかり、当然のことながら、ほかのものは、ケリーと、グーチであると見当をつけた。 ということは、3人の男たちは、そのうちひとりは、道義心のまったくないならず者だが、リチャード・ゴードンのあとを追って、すでに荒涼とした法律のない荒野に行ってしまったということだ! ヴァージニアは、自分がまにあわなかったという恐怖に襲われぞっとした。しかし、すぐれた知識と経験をもったゴードンは、ほかのものたちをはるかに引き離しているに違いないし、身軽に注意深く道を選べば、彼らがゴードンに追いつくか、帰り道の彼に出会うかする前に、自分は彼らに追いつくに違いないという、この希望が、彼女をささえた。心にこの考えをもち、ヴァージニアは、準備をいそがせ、いったん出発してしまうと、最大級のスピードで彼女のサファリ(探検隊)をせきたてた。 出発からほどなくして、彼女は雇い人の頭の男が、見たところ、彼女に忠実であると同時に、従順でなく、けんかっ早い傾向にあるサファリ(探検隊)の男たちを不充分にしか監督できないことに気づいた。その結果、つねに、この原因からくる不安が彼女につけ加わった。というも、それは、彼女自身の幸運だけにのみならず、彼女の使命の成功さえも同様に、脅かしていたからだった。 実際、最初の目に余る規律違反は、10日目に起こった。それは、隊商頭が、処理できないか、それとも、娘が気づかないまま許していたことだった。男たちは、まったく最初から、自分たちの身の上にふりかかった強行的な行軍にずっと不平を言いつづけていた。彼らが、はっきりとした合意のもとに、雇われたという事実にもかかわらず、彼らの義務の本質はこんなものだった。その日、昼休みのあと、ポーターたちは、めったにないほど、彼らの荷物を担ぐのが遅かった。そして、隊商頭があらゆる種類の厳しい脅迫によって、命令を実行しようと彼らの中にいくと、たくさんの、つぶやきやら、不平が起きた。男たちの何人かは、不機嫌そうに立ち上がったが、他のものたちは、隊商頭に従うために動こうともせず、彼をじろりと見て地面にすわったままだった。ヴァージニアは、少し離れたところで、サファリ(探検隊)が出発するのを待っていた。彼女は、起ったすべてのことの目撃者だった。彼女は図体の大きい真っ黒なヘラクレスが、興奮した隊商頭の命令に応えてのろのろと彼の荷物を持ちあげるのを見た。 まさにその時彼らの間で交わされた言葉を彼女は知ることができなかったが、突然、そのポーターは、すでに重い荷物を引き受けていた他の者たちにどなりながら、自分の荷物を地面に強く投げつけた。ひとりずつ、これらの者たちは、彼の例にならい、同時に、無能な隊商頭にたいして、興奮してあざけりと、侮辱の声をあげ、踊った。原住民の護衛である、一行のうちの武装した者たちが、彼らのライフル銃をたてかけて、隊商頭の狼狽に、歯をむきだしにして、笑った。この公然とした失敗を目撃して、ヴァージニアの心はがっくりきた。それは、純然たる反乱であり、彼女の隊商頭は、それを対処するのにどうやらまったく完全に無力であった。それは、すみかやかに武装している護衛たちにも広がるだろうと彼女は確信した。それというのもの、彼らの態度は彼らがポーターたちを支持していることを、示していたからだった。何かしなくてはならない、それも、すぐにしなくはならない、そしてまた、それをするのはほかの誰でもない彼女自身だ。 ヴァージニアは、いそいで決断した。彼女は急ぎ足で、自分とポーターたちの間のスペースを渡り、隊商頭とけんか腰のポーターの間に立つまで、見物人を肩で押しのけながら進んだ。彼女の姿をみると、彼らは、しばらく言い争いをとめた。ヴァージニアは、隊商頭の方を向いた。 「この男に言いなさい」彼女は言った。「彼はすぐに自分荷物を拾いあげないといけないと私が言ったと」 隊商頭は、その暴動者に彼女の命令を通訳した。彼は命令に従おうとせず、あざけるように笑っただけだった。とてもゆっくりと、ヴァージニアは、彼女の腰のホルスターから、リヴォルバー銃をひきぬいた。彼女は、ポーターの腹のくぼみのあたりにねらいをつけて、左手で、地面の荷物を指さした。彼女は何も言わなかった。彼女は、狙いをつけた武器の意味する脅しを必要とあれば、実行するという手段に身を任せた。そして、彼女は最後まで、その手段を支持した。 彼女の探検隊の運命は、彼女のポーターたちと、彼女を代表する隊商頭との間のこの小競り合いの結果にかかっていたそして、その探検隊の運命には、彼女につくすための旅にわが身をおいてくれたまさにあの見知らぬ人の人生も、ことによると、かかっていた。選択はない。彼女はしなくてはならない。彼女は無理にでも従たがわせないといけない。 そのポーターは、笑うのをやめた以外は、彼の荷物を引き受けるために、動こうとはしなかった。そのかわりに、彼の小さい目をひそめ、彼の重い下あごと、ぶらぶらした下唇を不機嫌そうに下げた。彼は、大きなけだものがその獲物に飛び掛ろうとする様子を突然娘に思い出させた。それで、彼女はリヴォルバー銃の引き金にかけた指を強く締めつけた。 「彼に言って」彼女は隊商頭に指図した。「反乱の罪は死罪よ。もし彼がすぐにでも、自分の荷物を拾い上げないのなら、私は彼を撃つわよ。まさしく、私の安全をおびやかすハイエナを撃つみたいにね」 隊商頭は言われたとおりのことをした。そのポーターは、励ましを求めるように囲んでいる彼の友人たちの顔を見た。彼はそれを見つけたと思い、ただちに、悪霊が彼にその白人の女性は撃つ勇気などないと囁いた。それで、彼は、威嚇するように彼女のほうに1歩踏み出した。 それは彼の最後の1歩だった。彼がそうするないなや、ヴァージニアは、発砲した。彼の腹めがけてではなく、彼の心臓に。 そして、彼は、前にくずれおち、彼女の足元に倒れた。彼をちらりともみず、彼女は、ほかのポーターたちのほうにくるりと向きを変えた。 「あなたたちの荷物を拾いなさい。そして、歩くのよ!」彼女は命令した。そして、彼女の言葉を理解することはできない彼らだが、少なくとも、彼女の狙いをつけた武器の脅しは誤まって解釈することはなかった。ひとりひとり、第1日目をすぎてからずっと見せてきたよりもずっとすばらしく敏速な動きで、荷物を背負い、一瞬ののちには、その小道を列をなして行進した。 そのサファリ(探検隊)は、まだ歯をむきだしにして笑っていたが、そのことに、ヴァージニアは、心から感謝した。 それからは、彼女が通訳として、主として高い地位の者を使いながら、彼女自身の隊商頭となった。 |