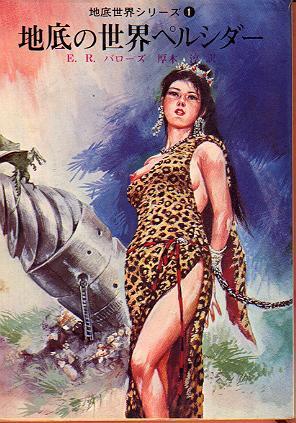 バローズは1913年の2月、すなわち「火星シリーズ」の第2巻と「ターザン・シリーズ」の同じく第2巻を脱稿した翌年に、一転して新シリーズの執筆を思い立ち、一気呵成にその第一巻を書き上げた。それが本書「地底の世界ぺルシダー」で、その14ヵ月後に〈オール・ストーリー・マガジン〉に発表され、全7巻に及ぶシリーズの皮切りとなった。
バローズは1913年の2月、すなわち「火星シリーズ」の第2巻と「ターザン・シリーズ」の同じく第2巻を脱稿した翌年に、一転して新シリーズの執筆を思い立ち、一気呵成にその第一巻を書き上げた。それが本書「地底の世界ぺルシダー」で、その14ヵ月後に〈オール・ストーリー・マガジン〉に発表され、全7巻に及ぶシリーズの皮切りとなった。地球外の惑星を舞台にしたスペース・オぺラ的な構想の「火星」や「金星」シリーズとは異なリ、本書の著しい特色をなすのは、むろん〈地球空洞説〉の採用である。ドーナツ状の中空の地殻という地球空洞説は一見、SF作家の突飛な発想になるもののように思われがちだが、実はその起源は意外に古く、世界中に分布する各国の神話、伝説にまでさかのばることができよう。迷路のように入り組んで下降する大洞窟や噴火口の深淵は、その先に何があるかと原始時代の人間を畏怖せしめたであろうし、また死者を土中に埋葬する慣習は、足下に広がる黄泉の国の存在を印象づけたにちがいない。近代における地球空洞説の沿革をたどれば、まず18世紀の中頃にオランダ語で書かれたルドヴィッヒ・フォン・ホルベルクの「地底世界への旅」 Journey to the World Under-Ground が最も古典的なものであろう。これはニコラス・クリミヴスなる主人公が、地殻に貫通した穴を経て地底世界を旅行し、そこの住人や地殻の内側に輝く太陽や多数の惑星を見聞するという体裁を通して当時の社会風俗への諷刺を試みた作品である。
それよりややおくれてドイツのラスペ(後に同じくドイツのゴットフリート・ビュルガー)が集成した有名な「ほら吹き男爵の冒険」のなかでも、主人公のミュンヒハウゼンがエトナ山の噴火口伝いに地底世界に達し、そこで火の神バルカンの怒りに触れて泉の中に投げ込まれたところ、地球の中心を通って出て来たところが南極洋という綺譚が語られている。最もスピーディな地底旅行といってもよいだろう!
19世紀にはいるとアメリカのキャプテン・クリーブス・シムズによる地球空洞説の論文が1826年に発表されているが、その六年前にアダム・シーボーンなる作者が「シムゾニア」という架空冒険記を発表している。これはフィクションで、南極にある開口部を通って海洋伝いに船で地球の内部に達し、そこに文明を持つ住民と二つの太陽、二つの月を発見したいきさつが述べられている。多分このシーボーンはシムズの変名であろうというのが今日の通説であるが、実はこのシムズの名前を閑却するわけにはいかぬ理由がある。それは、このシムズ説に触発されてE・A・ポオが初期にいくつかの作品を書いているからで、就中、「壜のなかの手紙」(1833)と「ハンス・プファアルの無類の冒険」(1835)がそれにあたる。前者に於ては南極の極点近くで、海水が轟々と落下する渦巻状の開口部がポオ一流の筆致で無気味に描かれているし、後者に於ては軽気球から望見した南極点の開口部が示唆されているというぐあいである。
さて地球空洞説はこうした沿革を経て、1864年フランスのジュール・ヴェルヌにより初めてSF作品として結実する。アイスランドの噴火口を経由して地底世界に到達するというテーマのこの有名な作品「地底旅行」は今さら紹介の必要もない。ヴェルヌの「地底旅行」の成功は多くの模倣者を生んだが、その延長線上にあって20世紀にはいって決定的な声価を占めるのが、すなわち本書「ぺルシダー・シリーズ」である。(バローズも極点にある地底の開口部というシムズ理論を本シリーズの3巻、4巻、7巻などで採用している)。
ところでバローズの作品が持つ人気の秘密とはなんであろうか? ヒーローやヒロインの持ついうにいわれぬ魅力、たとえば「火星シリーズ」のジョン・カーターやデジャー・ソリスといった人物創造の巧みさは、その一因であろう。戦闘場面の迫真力も、(空想冒険作家としては当然のことながら)みごとなものがある。しかし、こうした分析的な批評からはえてして忘れられがちなことだが、彼が常に空想的な別世界の創造にかけては並々ならぬ手腕の持主であることを、ここで特筆大書しておく必要があるように思われる。ジョン・カーターやデジャー・ソリスが絵空事の域を脱して読者の脳裏にまざまざと実在するのは、その背景にバルスーム(火星)というバローズががっちりと創造した虚構の世界が展開するからである。バローズは新世界の創造にあたっては風俗、習慣、文化、歴史、動植物から社会生態学に至るまで常に周到な構成をして作中人物の活躍を裏づけるが、本書ペルシダーの初巻もその例に洩れない。水平線がなく、頭上にせり上っていく海、静止した太陽によって時間と方位を喪失した世界、昼夜の別のない永遠につづく一日、地表とは丁度逆となった海陸の分布等、その描写の 適確さと着想の鮮かさは半世紀を経た今日でも少しも色褪せない。
ところで、バローズの本書をしてヴェルヌの亜流に終わらせないもう一つの点を指摘するならば、それは〈マハール族〉の設定である。地底世界ぺルシダーに於ては、人間は石器時代の状態に留まっており、それより優秀な知性の持主である爬虫類に使役され、彼らの食料にもされる家畜にすぎないのである。これは人間(即白人)だけが万物の霊長であり、その他の動物はすべて人間に奉仕するために創造されたとするキリスト教的世界観にたいする痛烈な皮肉であり、諷刺でなくてなんであろう。人間以上の知性の存在という仮定はSF的思考を弄する人間にとってはおなじみなものだし、現代に於てはアーサ・クラークの「地球幼年期の終わり」やピエール・ブールの「猿の惑星」などによって普及してしまったが、20世紀初頭においては、かなりショッキングな価値観の転倒ではなかったろうか。この辺は、空腹時に犬や牛を見て、ごくりと生唾をのみこむ習慣のないわれわれ農耕民族の末裔の想像以上のものがあったと思われる。20世紀初頭、というのは、白人種の全盛時代、日本を除く東洋の全土が植民地もしくは半植民地化された時期である。日本人などは、さしづめイエロー・サゴス程度にしか 見られていなかった時代であることを考えれば、バローズという人物が、単純な白人優越論者でなかったこともうかがわれて興味深いものがある。例えば「火星シリーズ」に於ては、ブラック・バイレーツなる優秀な黒人種が活躍するし、「失われた大陸」に於ては21世紀のアメリカに拮抗できるのは黄色人種の中国と黒人種のエチオピアだけなのだ。彼の作品の随所に白人としては些か自嘲的な未来観が語られているが、その端的な一例を「失われた大陸」から引用してみよう。