ERB評論集 Criticsisms for ERB
野田宏一郎「E・R・バローズの世界」
創元推理文庫「火星の巨人ジョーグ」解説より
Oct.1968
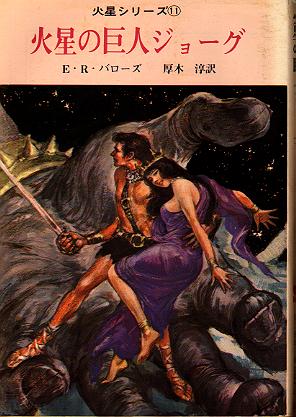 「船はしずしずと南東に流され、木造の部分が燃えて重量が減少するにつれてぐんぐん上昇していった。わたしは屋上にでると、船がしだいに遠ざかり、やがて遠い空のかなたに姿を没するまで何時間も見守っていた。広漠たる火星の天空に、操縦するものもなく火炎に包まれて漂う壮大な無人船。空中の火葬。その光景はまったく荘厳というほかはない。死と破壊の漂流船は、この奇怪かつ野蛮な緑色人の人生を象徴するものであり、船が彼らの敵意ある手中に落ちたのは運命のいたずらだった。……」(『火星のプリンセス』79ページ参照)
「船はしずしずと南東に流され、木造の部分が燃えて重量が減少するにつれてぐんぐん上昇していった。わたしは屋上にでると、船がしだいに遠ざかり、やがて遠い空のかなたに姿を没するまで何時間も見守っていた。広漠たる火星の天空に、操縦するものもなく火炎に包まれて漂う壮大な無人船。空中の火葬。その光景はまったく荘厳というほかはない。死と破壊の漂流船は、この奇怪かつ野蛮な緑色人の人生を象徴するものであり、船が彼らの敵意ある手中に落ちたのは運命のいたずらだった。……」(『火星のプリンセス』79ページ参照)
ジョン・カーターが火星にその一歩をしるしてから間もなく、緑色人たちは、突如あらわれたヘリウムの宇宙船に対して略奪の限りをつくしたあげく、その船に火を放つ。火星シリーズ全巻を通じて、もっとも壮麗な描写の一つである。このシーンの直後に、主人公ジョン・カーターは火星のプリンセス、デジャー・ソリスと運命の対面をすることになる。これ以後、3,000ページ、11冊、15編の火星シリーズは絶世の美女、醜悪な怪獣、怪力無双の豪傑が入り乱れて、息をつがせぬ壮大な絵巻を読者の前に展開することになるのである。
かつては、青々とした水を湛え、数々の財宝を満載したきらびやかな商船の行き交ったその海もいまや涸れ果て、そこにはただ、赤い砂と黄土色の苔におおわれた荒野がはてしなく続く。往時の繁栄した面影を残す廃墟の都市を割拠する赤色人や緑色人たちは、人工大気を頼りに細々と暮らしている。そして地下や山中にかろうじて生存する白色人や黄色人。彼らの生命を脅かし、つけ狙うのは凶悪な大白猿、人肉を好餌とする火星のライオン、バンスと火星ねずみ、アルシオである。
だが、火星人たちは、そんな苛酷な条件に押しひしがれそうな素振りは微慶も見せない。次々と登場する姫君や女奴隷は、すべて切ないほどまで美しく、男性はたくましく、寡黙であり、笑いながら命を捨てる。襲い来る身の毛もよだつ怪物を相手に一歩も退かず、ひしひしと取り囲む戦士の数が多ければ多いはど、そしてまた相手が剣の使い手であればあるほど、受けて立つ彼らは一段と生きる歓びにあふれ、決闘の真っただ中へ白刃をかざして突入するのである。
火星シリーズ全編の筋立ては、きわめて単純である。
……美しい女が他の種族に掠奪され、あるいは誘拐され、あわや彼らの壬妃に、奴隷に、実験材料に、男のなぐさみものにされようというきわどいところに、単身あるいは仲問と共に乗り込んで来た主人公が怪物を倒し、敵と斬り結び、飛行艇を駆って無事救出に成功する……まことにありふれた図式の飽きもせぬ反復だといえなくもない。
われわれ日本人にとって、庶民の少女が美しいというただそれだけの理由で権力者のなぐさみものにされてしまうなどという出来事は、つい百数十年前までは、いくらもあったことである。ちょっと思いついただけでも、つい先頃あらわれた江戸築城の際の人柱とおぽしき枯骨、中尊寺の藤原三代のミイラ、あるいは新田義貞嫌倉攻めの戦士のものらしき材木座人骨群などわれわれの身近なところで散見できる様々な事象は、火星の廃墟の地下に横たわるミイラや洞穴の奥深く山積みされた火星人の枯骨などよりはるかに豊かなイマジネーションをかきたてずにはおかない。
魔法を使ったという疑いで焚殺される哀れな女の断未魔の絶叫や、古城の奥深く秘められた拷問室の陰惨なムードがまだ色濃くこぴりついたヨーロッパの風土の中に育った人々にとって、ミイラ作りの老人アイ・ゴスや、裸女をこんがりと火で灸ることを趣味とする王(ジェド)グロンの描写がどれほどの迫力を持ち得るか? 白刃をきらめかして正邪を争うという火星人社会のモラルが、どれほどフレッシュなものとして彼らの目に映るか否か……?
いってみれば、火星シリーズの世界、バローズの構築したこの架空世界は、アメリカ大陸というからりとした風土の中ですくすくと育ったアメリカ人たちが、はるかな旧世界に思いを駆せて彼らの遠い祖先のいともおどろしく野蛮で怪奇な世界へよせる郷愁と渇望がその基調になっているのだといえる。バローズの世界はそんな意味からしてきわめてアメリカ的であり、それ以外のものではあり得ない。彼の作品がよく、ライダー・ハガードの系譜につながるものと言われることにも一理ありながら、むしろアメリカ独得の
Sword and Sorcery の世界、R・E・ハワードやJ・R・R・トールキンなどのほうにより近いというほうが妥当かもしれない。
自動操縦の飛行艇、人工大気、地下鉄道、潜水艦などを実用化するだけの能力を持ちながら装身具と刀剣類を身につける以外は全裸だという火星の男女。ラジウム銃や放射線砲まで開発しているというのに合戦のときは、八本足のソートにうちまたがって長剣を振りまわし、死ぬまで戦うのがモラルだという奇妙な社会。
それは当時のヨーロッパおよびアメリカの社会基準が決定的な概念として考えていた「高級な」民族の特徴と「低級な」民族との特徴を人類の進歩途上における一事象としてミックスした「高貴な野蛮人」という人間像を火星世界に登場させたのだと思えば思われなくもない。事実、低級な野蛮人とヨーロッパの紳士という二つの理想像の合成がバローズの手によってなされているからである。それは言うまでもなくターザンである。
だが、この火星シリーズを通してバローズは、そのいともアンバランスな社会の構造とその社会に住む火星人との相関について、さほど深い掘り下げを行なっているわけではない。
滅びゆく火星の風土の中で形成された火星人の特質について、バローズはジョン・カーターに次のように語らせている。
「この哀れな火星人たちが、あらゆる繊細な感情や、高度の人道的な本能を喪失したのは何代もつづいてきたこの恐ろしい習慣(適者生存のために卵のきぴしいチェックを行なうことを指す)が直接の原因だと思う。生まれたときから父親や母親の愛情を知らず、家庭ということぱの意味を知らないのだ。子供たちは、自分が生きるに適しているということを体格と狂暴性で示すことができるようになるまでは、ただ生かしておいてもらえるだけなのだということを教えこまれる。……彼らはごく幼少のころから多くの辛酸をなめるが、涙ひとつこぼさない。
……だが滅びゆく惑星上で、彼らは苛酷な生存競争をしているのだ。……」(『火星のプリンセス』70ページ参照)
笑うことが拷間、苦痛、死を意味する世界。その中に偶然のことから住むようになったジョン・カーターはこの粗暴な正義の支配する世界を矛盾(パラドックス)の惑星と呼ぶ。そしてさらに、緑色人の親友タルス・タルカスに向かって言うのである。
「……こんなことでは滅亡するその日まで、いまあなた方につかえている愚かな野獣どもとほとんど変わらない生活をつづけていかなくではならないのですよ! 文字を持たず、芸術もなく、家庭もなく、愛もない民族、あなた方は何世代にもわたる恐ろしい共同体思想の犠牲者です。……」(『火星のプリンセス』93ページ参照)
だが、まことに異様なこの惑星世界におかれ、彼らの一員として生活を始めた地球人のこの叫ぴも、火星シリーズの話の進行と共にたちまち雲散霧消していくのである。
ジョン・カーターが火星人社会に同化してしまったからか? いやそうではない。責任の大半はバローズのほうにあるのだ。第一作『火星のプリンセス』の初頭に出てくる火星世界の設定とはうらはらに、あまりにも地球人くさい、あまりにも繊細すぎる感情を持った妙な火星人ばかりがつぎつぎと登場しすぎるのである。奇妙な火星人のモラルと慣習が支配するこの社会におかれた地球人がどんな行動を示し、火星人がそれに対してどんな反応を示すか――『火星のプリンセス』の中にちらりと見せる、まぎれもなくSF的なこの発想は、そのために残念ながらたちどころにけし飛んでしまっているのである。
だが、バローズの世界の本質にとって、そんなことはどうでもよいことなのだ。1930年6月号の〈ライターズ・ダイジェスト〉誌上に彼はいみじくも次のように書いている。
「わたしが19年問にわたってフィクションを書きつづけ、曲りなりにも成功したといい得る結果を得たのは、わたしが面白い話を楽しく読者に伝えようと、ただ、それだけのことに全力を集中してきたのが原因である。わたしはつねに最良の作品だと自信の持てる作品を発表してきたつもりだ。それは本を買ってくれる読者に対する作家の重大な義務だと思うのだ。わたしはこれまで一度として、自分の作品の文学的価値がどうのなどという錯覚にとらわれたりすることはなかった。わたしは、自分の能力の許す限り最良の作品によって、読者をできる限り満足させることにだけつとめたのである。わたしはすべての人に自分の作品が満足してもらえたなどとは考えていない。だが、わたしの考えを知る読者で、わたしの作品にひどく失望した人はそれほど多くないはずだと信じている……」
バローズの世界はまさに、この言葉に要約されつくしていると言えよう。
さらに、またバローズは次のように言っている。
「わたしがなぜフィクションを書くようになったか――という質問をよく受けることがある。最大の理由は――金が欲しかったからだ」(《The
World Magazine 》1927年10月27日号よリ)
1875年の9月1日、シカゴで生まれたバローズが、1912年に処女作『火星のプリンセス』を発表するまでの37年間の人生はまさに辛苦の連続であった。1910
年頃には妻の宝石や衣類を売り払って飢えをしのいだとさえいわれている。そんなある日、ふと目にした新聞のあまりにもつまらない連載小説に発奮して、これで金になるなら自分だって――というのが執筆生活にはいった直接の動機だと彼は語っている。
もちろん、これを額面通りに受けとることは軽率に過ぎるだろう。兵隊や勇しいことが大好きで職を転々として赤貧にあえぐ三十男が、ふと発奮したくらいのことで、これだけの作品の書けるわけがない。彼の資質もさることながら、どこかで、こつこつとなにかを身につけてきたその姿勢があればこそのことである。
だが、とにかく「本を買ってくれる読者をたのしませるために全力をつくす」というそのあけっぴろげな執筆態度こそは火星シリーズの本質を物語ってあまりある。火星シリーズの魅力はまさにその語り口の巧みさと奔放なイマジネーションをおいて他にはなく、そしてその点においては、以後にあらわれた有名無名の数知れぬ模倣者たちの追随を今日まで頑として許していないのである。
1912年、1913年の両年に発表された火星シリーズの初めの3作『火星のプリンセス』『火星の女神イサス』『火星の大元帥力ーター』が連作の形式をとり、3作目をもって完結していることはいまさらここに言うまでもないだろう。
《はじめて読まれる方ヘ》
南軍の騎兵大尉ジョン・カーターはインディアンに追いつめられ、アリゾナの洞窟から、ある夜、忽然と火星へ飛来した。火星では発達した科学力を背景に四本腕の戦闘的な緑色人や地球人と同じ赤色人などが戦闘に明け暮れていた。その渦中に飛ぴこんだカーターは緑色人皇帝タルス・タルカスの友情を得て、大活躍の末、ヘリウム帝国のプリンセス、絶世の美女デジャー・ソリスと結ばれたが、そのとき、火星は大気の供給がとだえて絶滅の危機に瀕した。カーターは身を挺して危機を救ったが、その瞬間、気を失い、意識を回復したときはアリゾナの山中にもどっていた。そのまま地球で十年の歳月が流れた。しかし、永遠の恋人、デジャー・ソリスとの再会の情もだしがたく、その念願がかなってカーターは再度火星へ飛来した。到着地点は火星の楽園とされるイス河伴のドール谷であったが、実はそこは吸血植物人間や肉食大白猿の棲息する死の谷であり、ホーリー・サーンと呼ばれる白色人、ファースト・ボーンの黒色人、生と死の女神イサスの支配するところでもあった。カーターはその地で美しい女奴隷のスビアを救い出し、彼の不在中に生まれていた息子力ーソリス、僚友タルス・タルカス
とともにイサスに挑み、邪教の偶像を粉砕した。しかし、イサスの奸策によってデジャー・ソリスとスビア、サーンの教皇の娘ファイドールの三人は太陽宮に幽開されてしまった……。
以上が、『火星の大元帥力ーター』の中扉裏に掲載されている1、2巻の梗概である。 この一年間は太陽宮に閉じこめられて外へ出ることができないというクリフ・ハンギングにつづく第3作『火星の大元帥力ーター』では、サーンの教皇マタイ・シャンに拉致されたデジャー・ソリスをドール谷の緋色の大平原から北極の雪原の果てまで追って、ついに黄色人を平定してソリスを救い出す。
まことに息をもつかせぬアクションにつぐアクションである。一般にこの3作をもって火星シリーズの代表作とするのも故なしとはしない。だが、火星シリーズ11冊15編を一つの系列としてながめてみると、第1作は第1作だからさておくとしても、わたしにはこの3作が火星シリーズ中の最高傑作だとはどうしても考えられない。
カナべラル・プレスの編集者リチャード・リュポフはその評論の中で、もし火星シリーズがこの3編だけだったならばその名声はもっと高かったであろうと言っているが、それはあくまでもバローズ・ファンのバローズ観からくるもので、もし本当に彼が火星シリーズを3編しか書かなかったら、少なくとも火星シリーズに対するSF側からの評価がかなり低かったであろうということは想像に難くない。
10年目に地球から火星にもどってきたのはイス河のほとり、折しも彼の行方を求める親友タルス・タルカスは世にも奇怪な植物人間との決戦の最中――に始まる第2作。たちまち助太刀に飛び込むジョン・カーター。この出会いの会話といい情況といい情景描写といい文句のつけようのないほどの快適なできである。植物人間のグロテスクさ加滅も申し分ない。そして断崖をよじのぼって危地を脱した二人が、デジャー・ソリスを追ってイス河の奥地へと進もうとするまでは実にいいのである。なにしろ千年の寿命を全うした火星人たちが巡礼に出て、一人たりとももどってきたためしがないという、象の墓場を思わすこの無気味な設定はすでに『火星のプリンセス』の中にもあらわれているし、そこですっかり火星シリーズのファンになりきっている読者をこの第2作にひきつづきひっぱって行くには充分すぎるほどよくできた段取りである。鬼が出るか、蛇が出るか、バローズのことだから、さぞかし妖しい身の毛もよだつ無気味なイマジネーションが展開するだろうと読者が胸をときめかすのも当然である。
ところが、そのイス河の彼方、ドール谷のイサス宮殿を守る神官サーンの連中というのが俗物なのだ。巡礼者の持ち物を掠奪し、白猿にその死体をくわせて両者の生活を維持するために、この伝説を太古にでっちあげたのだという事実においてはもう何をかいわんやの感一入である。しかも彼らを脅かすブラック・パイレーツ(なんと陳腐な名であることか)なる近代的な海賊が現われるというイメージの貧困さには腹も立たなくなってくる。女神イナスが人肉を好んで食べる老婆で、闘技場で人間を戦わせるという設定もおざなりである。そのために、カーターがはじめて自分の息子力ーソリスとめぐり会うくだりまでが、はなはだしく興をそぐ結果に終わっている。
しかも、話はまったくこのペースのままで『火星の大元帥力ーター』にまでつづくのだ。〈腐肉の洞穴〉もおどろおどろしいだけのことで、北極の磁柱の電磁石もさしたる迫力はない。捕えられたり逃げ出したり、化けたり化けの皮をはがされたりの連続の揚句がめでたし、めでたしと相成る始未。
それゆえか、「22年前、わたしは裸一貫の風来坊として、この見知らぬ野蛮な世界に放りだされた。あらゆる種族と国家は、他のあらゆる肌色の人間に対し、間断のない紛争と闘争をいどんでいた。現在では、わたしの剣の威力と、剣の威力が得させてくれた友人たちの忠誠によって、黒色人や白色人、赤色人や緑色人が、平和のうちに胸襟をひらいて交際している。バルスームの全国家が一つになったわけではない。しかしその目標めざして大きく一歩ふみ出したのだ。……」(『火星の大元帥カーター』254ページ参照)と、いう結びの部分の説得力はあまりない。だが、火星シリーズを読むときにこのようなことを考えるのは野暮なのだろう。また、このようなことを考える向きは、バローズの作品を読まないほうがよいのだ。
この三部作が完結してから2年目、バローズは『火星の幻兵団』を発表した。1916年のことである。彼は『火星のプリンセス』を発表した翌年、1913年に発表した〈ターザン〉によって爆発的な反響を呼ぴ、すでに盛名をほしいままにしていたが、そこで彼が苦しんでいた問題――同じ主人公が活躍するフレッシュな作品をつぎつぎに送り出すことの苦しさ――を解決する手段として、この第4作にカーターの息子であるカーソリスを登場させたことは、まことに賢明なことであったと言わねばならない。『火星の幻兵団』は作品としては小味である。筋立ても地球社会の色恋の三角関係をそのまま火星に持ち込んだようなオープニングを持つ火星シリーズの一エピソードに過ぎないが、この作品でバローズははじめて――とあえて言うが――彼ならではの壮烈なイメージをはじめて炸裂させたのである。それは観念を具象化することによって現われる幻の大軍である。この発想は『西遊記』にも似たようなものがあらわれているので、けっして彼のオリジナルというわけではないが、この作品のストーリーを展開するにあたって、幻の大兵団という発
想は見事な実を結んでいる。とくに幻兵団の中の一人がついに現実の存在になってしまうというくだりは秀逸である。この作品の中には他にカーソリスが改良したというオート・パイロットや障害回避機と称するラジウム応用のレーダーをはじめとして、もろもろのSF的な小道具が現われるが、この幻兵団の持つSF的なイメージの前ではまったく色あせてしまう。そして「おまえは虚妄の存在だ!」と、カーソリスをののしるロサール皇帝の滑稽な独りよがりの姿は、バローズが地球人社会を意識して書いたものかどうか……興味あるところである。
バローズのイマジネーションの振幅は、つづく第五作『火星のチェス人間』において一つのピークを形成したと考えられる。すなわち、首なし人間族のライコールとそれに寄生して生きている怪物カルデーンである。
「われわれのからだはいまより大きく、頭はもっと小さかった。……」と、人間の頭にクモ状の足が生えただけという、見るも無気味なカルデーンはさらに言うのである。「……われわれもまた地上へ出かけて食物を手に入れる必要がおきた。これはわれわれの弱い足には重労働だった。そこで、われわれはそういう原始的なライコールの背に乗りはじめたのだ。……時がたつにつれて、ライコールの脳はしだいに小さくなり、もはや目や耳を使う必要がなかったから、それらも退化してなくなってしまった。……ライコールは後足で(つまり人間のように直立して)歩くようになった。カルデーンがなるべく遠くを見られるようそするためだ」(『火星のチェス人間』103ページ参照)
このライコールとそれを支配する奇怪なカルデーンが跋慮するバントウームの世界はまさにバローズならではのものであろう。この作品にはマナトールのミイラ作りの老人や、人間同士が命をかけて女を争うチェス、ジェッタンなどの趣向も出てくるが、この怪物の怪奇さにくらべれば物の数ではない。
「ちょうどわれわれが、動物を飼育するさいにその肉体的な特性を遺伝させるように、カルデーンたちは自分自身を飼育して、記憶や回想力をふくめた精神的な特性を遺伝させるのだ。……われわれの主観的な精神の中には、祖先の印象や経験の多くが存在していることは間違いない。これらは、夢の中でだけわれわれの意識を刺激することもあるし、また、われわれは現在の存在の過渡的な段階をかつて経験したのではないか、という、漠然とした、しかし執拗な暗示となることもある。ああ、もしわれわれにそうしたことを思いだすカさえあったなら、こうした疑間も氷解することだろう! そうすればわれわれの前には、現在までつづいてきた無限の過去の、すでに忘れ去られた物語が展闘するだろう」(『火星のチェス人間』207ページ参照)というジョン・カーターのつぶやきは、この作品を派手なアクションだけの読み物から、SFの萌芽を根強く含んだ作品へと止揚している。惜しむらくは、そのつぶやきがつぶやきだけに終わっていることであるが、今日、バローズの作品に対してSFの側からその点を衝くことは酷というものであろう。
バローズは、この火星シリーズにおいて、地球人と断絶した新しい世界を構築し、その世界を地球人の目を通して描くことを意図しながら一ついに彼は地球人たちと訣別することができなかったのだった。回を追うたぴに、第一作にくどいほど描かれている火星世界の環境条件の中にでき上がった火星人のイメージは希薄になっていき、いとも地球人臭い火星人ばかりが登場することになるのである。しかも、善玉はすべて気は優しくて力持ち、悪玉のほうはとにかくせっせと悪事に励んでいるという、きわめて単純なパターンの人物が多い。全編15編の火星シリーズに登場する人物が何百人いるか分からないが、記憶に残るようなユニークな個性をもった者は数えるほどしかいない。
わたしが一番好きな登場人物は、第7作『火星の秘密兵器』にあらわれる気違い科学者(マッド・サイエンティスト)、フォル・タークである。
『「ホーイ!」彼は叫んだ。「わしは平和など望まん。わしは戦争を望むのだ。戦争! 戦争じゃ!」』(『火星の秘密兵器』200ページ参照)と強烈な台詞を飄々として吐き散らすよばよぼのこの老人、モラルも節操もなく、ただ得体の知れぬ発明と取り組んで喜々としているこの人物は、全火星シリーズ中でもっとも魅力的な人物だと思う。これだけのキャラクターを描き得るのなら、なぜ、もっとこの線を深くつっこんでくれないのかと残念でならない。同じような不満は緑色人サーク族の皇帝(ジェダック)タルス・タルカス、『火星の透明人間』にあらわれる殺し屋のウル・ジャン、そして衛星サリア(フォボス)の皇后(ジェダラ)オザラなどにも感じられることである。
これをバローズの限界ときめつけることはいともたやすいことだろう。だが結局、彼ははじめからの姿勢、つまり人物の描き分けに腐心するあいだに、少しでも強烈なイメージを展開するほうに創作の比重をかけるという行き方を貫いていたと考えられる。
ところで、このイメージの展開の方向は、第六作以降にはっきりと変わってきていることに気がつく。つまりSF臭とでもいったようなものをバローズが明確に意識しはじめていることである。それが今日、言われているところのSFのジャンルに包含されるとは言わないが、当時としてはサイエンス・ロマンスのジャンルの中に明らかに含まれる性質のものへと変質しているのだ。面白いことには、この分岐点をなした第6作『火星の交換頭脳』が、ヒューゴー・ガーンズバックの依頼によって執筆されていることである。1926年に世界初のSF専門誌《アメージング・ストーリーズ誌》を創刊したガーンズバックが、翌年《年刊アメージング・ストーリーズ》を出すにあたり、その芯となるべき作品の執筆者にバローズを選んだのである。表紙には美女ヴァラ・ディアを手術しているラス・サヴァスの姿がF・R・ポウルの手によって描かれており、今日、ファンのあいだで非常な高値で取引きされている。
高値はよいとして、ガーンズバックはバローズをどう評価していたか? 残念ながら当時を物語る資料はまったく残っていない。商業政策上、ガーンズバックがバローズに白羽の失を立てたことは想像にかたくないが、同時にまた、作品の内容について彼がいろいろと注文をつけたことも充分に考えられる。当時のSF界の情況から考えてみると、人間の脳を移植するという発想は、それだけで充分にセンス・オブ・ワンダーを読者にひきおこし得たことはまちがいないし、これがバローズの手によって料理されるとなれば、この企画、あたらぬ方がおかしいというものである。原稿料としては1,200ドルが支払われ、十万部発行されたものがほとんど完全に売り切れたという。これにカを得て、ガーンズバックは年刊を季刊に切りかえている。
しかし、ガーンズパックはおそらくこの作品に満足はしなかっただろうと思う。とくに後半、巨神タールと妖婆ザザのくだりは陳腐もここにきわまった感がある。おそらく、ガーンズバックにデッド・ラインを引かれてひたすら書きまくった感が強い。むしろ、彼にしてみれば、バローズをして豪傑以外の人物を主人公にした作品をはじめて書かせただけでも大成功であったと言わねばならない。
自らの脳を若々しい肉体へと、助手の手によって移殖させたラス・サヴァスが「わしの肉体の若さは頭脳の古さと調和しない」と、つぶやくところがあるが、つい先頃、青年の心臓の移殖を受けた老人が他の老化した臓器と若い心臓とのアンバランスに苦しんでいるという新聞記事を読んだとき、このくだりを思い出して、にんまりとしてしまった。
第7作『火星の秘密兵器』以降は、ふたたびバルスームの戦士と美女とが主人公として登場はするのだが、申し合わせたように各作品の中にマッド・サイエンティストないしは、それに近い人物があらわれるという事実と、第6作におけるガーンズバックの影響との相関は軽々しく論ずるわけにはいかない。《年刊アメージング》の大成功以来、バローズがSF畑のファンの存在を意識しだしたことは見逃せないことであろう。前記のフォル・タークのキャラクター、そして彼の発明になる透明自動ホーミング・ミサイルの登場などはその所産だといえる。またいっぽうで、一般バローズ・ファンヘのサービスもけっして忘れてはいない。これまでも淫蕩な悪王の皇帝(ジェダック)はたくさんあらわれるが、ここにあらわれる皇帝(ジェダック)グロンはその中でも妖しさにおいては随一のものだし、人工的に不具にされた裸女の踊りや、生きたまま烈火に灸られる裸女のくだりのグロテスクさもかなりのものである。
キャラクターの面白さを別にすれば、マッド・サイエンティストとして、もっとも興味があるのは第8作『火星の透明人間』にあらわれるファル・シヴァスであろう。彼は美女を生体のまま解割して大脳の活動を研究し、これをもとにして人工頭脳を完成し自動宇宙船をつくりあげるのだが、これをサイバネティックスの萌芽だといえば贔屓の引き倒しになるとしても、ストーリーの展闘上、この発想の占めるウエイトは非常に大きく、しかも充分説得力がある。これを側面から支えている秘密暗殺ギルド、サリアの透明人間、そして父をジョン・カーターの軍勢に殺された美女ザンダとの世話場など相変わらず退屈することは絶対にない。
第9作『火星の合成人間』には、ふたたびラス・サヴァスがあらわれる。個性らしきものはまったくないが、おそらく、彼の専門領域である人体の改造、脳の移殖、人工生命などにバローズが興味を覚えたためであろう。自分の脳を醜いサイボーグに移殖されたため、思いのたけを恋人に打ち明けられないという月並みな筋立ては、めずらしくバローズものにしては頂けない。ただ、合成人間をつくる地下工場がひとりでに動き出して、できそこないの奇怪きわまる人間のかけらが、つぎつぎと増殖しだすくだりの無気味さは全シリーズ中随一のものだろう。徐々に工場いっぱいにふくらみ、ついに扉を破り、やがて地下道にまではみ出して行く合成人間がつぶやく得体の知れぬ独語がザワザワと聞こえてくるという、ぞっとするような奇怪なムードが、いわば持続低音のように話の背景にずっと鳴りつづけているあたりは実にいい。
1933年12月6日、バローズは33年間の伴侶であった妻のエマとの離婚が成立した。苦境時代には自分の宝石を売り払ってまで共に苦労しあった糟糠の妻と、功成り名遂げた今、如何なる理由で別れたのか、その真相は周囲の人々もはっきり言いたがらない。だがバローズの心はかなり前から、ターザン映面の関係スタッフの一人、アシュトン・ディアホルトの妻、フローレンスに傾いていたことはまぎれもない事実である。そして、1934年ディアホルトと離婚したフローレンスは1935年5月にバローズと正式に結婚したのであるが、この結婚も6年しかつづかなかった。1941年3月18日、ハワイのホノルルを永住の地に定めた二人が建てた邸宅で、フローレンスは一方的に離婚を申し出た。理由はお定まりの性格の不一致と精神的虐待であった。
彼女は新聞記者に対してこう語っている。
「彼は一人で生活するのが好きなのです。エド(エドガー)はこの結婚を後悔していますし、わたしどももそれぞれ、自分の道を選んだほうがしあわせだと感じているのです」
同じその3月の《アメージング・ストーリーズ》誌に載った The City of Mummies
(『火星の古代帝国』の第一部を形づくる「古代の死者たち」)の冒頭でジョン・カーターが次のように書いているのは、はたして己れの述懐との偶然の一致であろうか。
「人間というものは本能的に集団生活を営むようにできてはいても、時として切実に孤独がほしくなることがある。わたしは人間が好きだ。家族や友人や部下たちとともにいるのが好きだ。そしてたぶん、それほど仲間づき合いが好きだからこそ、時には同じ程度に一人になりたくなるのてあろう。……それにわたしも人間であるから、とくと反省して、二度と繰り返さないようにしなければならぬ過ちも、多々おかしているのだ」(『火星の古代帝国』13ページ参照)
ターザン、とくにその映画化権によって巨万の富を得たバローズが1930年代末、ホノルルにその永住の地を定めた心の底にあったものはおそらくその感慨にちがいない。
この1941年の春から秋にかけて、第10作を形づくる他の3部「火星のブラック・パイレーツ」「火星の冷凍人間」「火星の透明人間」のいずれもジョン・カーターとその孫娘を主人公にした中編が、いずれも《アメージング・ストーリーズ》誌に発表されている。またそれに先立って1月号の同誌には〈火星の巨人ジョーグ〉が掲載されている。同工異曲といってしまえばそれだけのことで、バローズの嫌いな人はきっとうんざりしてしまうことだろう。だがバローズの好きな人はそれぞれにけっして退屈することはない。娯楽臭のきわめて強い当時の《アメージング》誌のカラーにぴったりの内容であり、ポーの『ヴァルデマール氏の病気の真相』を思わせるミイラの復活、強力なテレパシーの送信機による殺人、人的資源を氷結して侵略開始の日に備える冷凍人間、そして人間の体を完全に透明にしてしまう丸薬、人間の脳を集めてつくりあげる巨大な戦士など、よくもこうまでつぎつぎに思いつけるものだと感心しないではいられない。やはりバローズのバローズたる所以以外のなにものでもない。
勇ましいことが大好きなバローズの住むハワイをきっかけにして太平洋戦争が勃発したことは皮肉と言えば、まことに皮肉なことであった。悠々自適とはいいながら齢、すでに70歳、第2の結婚に破れて以来めっきりと老いの目立ち始めたバローズにとって、太平洋戦争は、心の底に秘められていたジョン・カーターの熱っぽい闘志を、さながらかきたてる残り火のように燃え上がらせたのである。真珠湾をすっぽりと包み込んだ炎がまだ消えぬうちに、はやくも彼は司令部に出頭して戦時報道要員としての登録を行なっている。
バローズが報道特派員として太平洋地域に従軍したのは、1944年初頭である。すでにアメリカ側がマリアナ諸島へ向けてじりじりと押しもどしを開始した頃のこと、ガダルカナル島からタラワ島ヘ、そしてクエゼリン環礁へと、つぎつぎと玉砕して行く日本側の拠点へとバローズは海兵隊と共に進んだのである。
クエゼリン環礁へ進出した陸軍航空隊のB24に同乗して、カロリン群島の日本軍基地の空爆に参加したときの様子を、同機の爆撃手だったO・R・フランクリンは次のように回想している。
「バローズは特派員の徽章もなにもついてないカーキ色のシャツにズボン、それに野球帽といういでたちで乗り込んできた。……われわれが500ポンド爆弾を6発積んで、ジャルイト島の日本の海軍基地上空へ進入すると、75ミリ高射砲が猛烈な勢いで撃ってきた。わたしは機首の爆撃手席にいたし、バローズは右側の機銃座にいたから表情はわからなかったが、インターコムを通して高射砲の炸裂位置を静かに知らせていた。『右! 高い。左、かなり低い! 大分うしろに一発! ……畜生奴! 風に帽子を飛ばされちまった! なにしろ、戦争がはじまってから髪を刈ってないんだ! 顔にはりついて! なんにも見えない!」……次の日には、ビキニ環礁の日本海軍の通信基地を空襲したが、このときにはまったく対空砲火を受けなかったので、バローズはひどくがっかりしたようだった。彼は作戦に参加することを本当にエンジョイし、熱狂し、そして一生懸命だった。そして彼は、われわれがこれまで作戦行動を共にしたどんな特派員よりも、気分的にしっくりといく愉快な気分の男だと話し合ったものだ……」
同じ頃、太平洋戦線やヨーロッパ戦線には、バローズの作品に血を湧かした青少年たちもたくさん従軍していた。当時サイパンから東京空襲に両かうB29の中にも「火星のプリンセス」号のニックネームを持った機体があったほどである。ノルマンディの上陸作戦に参加したある兵士は当時を回想してこう書いている。
「あの悪夢のような日々をわたしが兵士として正しく生き抜くことができたのはジョン・カータ−のお陰だった。こんなとき、ジョン・カーターならどうするだろう。お手本はジョン・カータ−だぞ。そんな思いの数々がわたしを支えてくれたのである」
第二次大戦は終わった。平和が訪れることはすばらしいことだが、バローズの心の中にできた空洞を、風が冷たく吹きすさぶのは如何ともしがたい事実であった。1941年に出た4作が『火星の古代帝国』の題名で刊行されたのは1948年のことであるが、あらためて書かれた導入部の中で、バローズと出会ったジョン・カーターは言うのである。
「ねえ、きみはわたしが顔を知っている地球人の身内の最後の人だ。時折り、わたしはきみに会って話をしたくてたまらなくなり、たまには――こうして――その気持を満たすことができるのだ。きみが死んでしまえば、そしてそうなるのもあまり先のことではないのだが、わたしには地球とのつながり――昔の生活の場にもどる理由がなくなってしまう」
「うちの子どもたちがいますよ」わたくしは彼に思い出させた。「あの子たちはあなたの血縁です」
「そう、わかっている。だが、子どもたちはわたしを恐れるかもしれん。結局のところ、わたしは地球人の目には幽霊のようなものに映るだろう」
「うちの子どもたちは違いますよ」わたしは保証した。「あの子たちはわたくし同様あなたをよく知っています。わたくしがいなくなったら、たまには子どもたちに会ってやってください」(『火星の古代帝国』9〜10ページ参照)
彼はうなずいて、「たぶんそうするよ」となかば約束した。……
1950年3月19日、月曜日の朝、心臓疾患のためベッドについていたバローズは、往診の医師と元気に話していたが、突然、読みさしの新聞が彼の顔をおおった。そして医師が駆けよったときには、すでにこときれていた。享年74歳、エドガー・ライス・バローズはこうして死んだのである。
〈火星シリーズ〉は1950年代未に、各社がペーパーバック版で出版しはじめたのを契機としてファンの数は激増した。40年近くにもわたって繰りひろげられた火星世界の壮大無比な大絵巻は、きっとこれからも数多くの読者を熱狂させることであろうし、ジョン・カーターの不屈の精神は未来を背負って立つ青年たちの心の中に、彼の好きな言葉同様に脈々と生きつづけることであろう。
――われわれは未だ生きている!――
ホームページ | 語りあおう
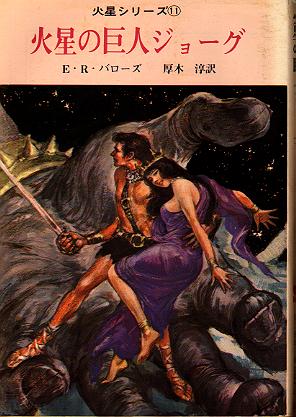 「船はしずしずと南東に流され、木造の部分が燃えて重量が減少するにつれてぐんぐん上昇していった。わたしは屋上にでると、船がしだいに遠ざかり、やがて遠い空のかなたに姿を没するまで何時間も見守っていた。広漠たる火星の天空に、操縦するものもなく火炎に包まれて漂う壮大な無人船。空中の火葬。その光景はまったく荘厳というほかはない。死と破壊の漂流船は、この奇怪かつ野蛮な緑色人の人生を象徴するものであり、船が彼らの敵意ある手中に落ちたのは運命のいたずらだった。……」(『火星のプリンセス』79ページ参照)
「船はしずしずと南東に流され、木造の部分が燃えて重量が減少するにつれてぐんぐん上昇していった。わたしは屋上にでると、船がしだいに遠ざかり、やがて遠い空のかなたに姿を没するまで何時間も見守っていた。広漠たる火星の天空に、操縦するものもなく火炎に包まれて漂う壮大な無人船。空中の火葬。その光景はまったく荘厳というほかはない。死と破壊の漂流船は、この奇怪かつ野蛮な緑色人の人生を象徴するものであり、船が彼らの敵意ある手中に落ちたのは運命のいたずらだった。……」(『火星のプリンセス』79ページ参照)